社会
Social
人間が、人間らしく生きる環境
Social
人間が、人間らしく生きる環境
2024.06.28
「COVID-19騒動」以降、日本の医療の実態について、勇気をもって糾弾する医師が急増しているようです。
今回は薬漬けの日本の医療に異を唱え、減薬・断薬したいと願う多くの患者のために「薬やめる科」を創設した松田医師による解説をご紹介します。
松田医師が長年の臨床現場で見たのは、根拠の薄い基準値によって病気にさせられた大勢の「患者」たちと、その治療薬をめぐる不自然な構図でした。
松田史彦(まつだ・ふみひこ)医療法人社団東医会松田医院和漢堂院長
1987年聖マリアンナ医科大学卒業。熊本大学医学部の麻酔科、同第2内科、東京女子医科大学附属東洋医学研究所を経て、熊本に松田医院を開業(2007年より医療法人社団東医会松田医院和漢堂)。熊本赤十字病院・NTT九州病院では漢方専門外来を担当。
西洋医学が引き起こす問題に対して、食生活改善、減薬・断薬、漢方針、鍼灸、心理療法などを組み合わせた統合医療で対応している。
読者の皆さんは、日本が“薬大国”であることをご存じだろうか。
「世界最大のシンクタンク」とも呼ばれるOECD(経済協力開発機構)の統計によると、2020年における日本の薬剤費はOECD加盟35カ国中で大国・アメリカの3位よりも多い2位だった。
日本でこれほど薬剤が多用されている最大の理由として、日本には皆保険制度が整っていることが挙げられるだろう。
そのため日本人は「病気になったら病院に行って薬をもらう」ことが常識になってしまっている。
まさに“薬漬け”である。

しかし考えてみてほしい。
人間の体はいわば化学工場のようなもので、生きているかぎり常に、60兆個もの細胞が体の中で化学反応を繰り返している。
一方、薬も化学物質であるから、これを化学工場の中に放り込めば、1カ所だけに作用することなどありえない。
「〜遮断薬」「〜阻害薬」「〜拮抗薬」など薬の名称は、化学反応に介入しますという証拠である。
たとえば胃薬を飲んだとしても、胃だけに効くわけではない。
肝臓で分解されたり、血液に入って体中を巡ったりする。
そうした化学反応は同時並行的に体中のあちこちで行われ、多重の反応が常に影響しあっていく。
さらには、個人の病状やその日の天候(周囲の環境)などによっても同じ反応が出るわけではない。
そして化学反応の過程のどこかで、期待される「薬の効能」が現れたとしても、細胞を壊したりアレルギー反応を引き起こしたりすることがあるし、使う量を間違えればすべての薬が有毒物質となりえる。
そうした反応の全てを把握することなど誰にもできないし、一度効いた薬であっても次に使用したときには牙をむくことさえある。
つまり薬は、いつでも”一か八か”、賭けのようなもの。
そしてそれは「人工的に作られた薬」だけでなく、「自然の中に存在する薬」にもいえることなのである。
だからこそ私たちは、飲み薬にかぎらず塗り薬や貼り薬など、どんな薬を使用するときにもそのことを肝に銘じておく必要があるのだ。
さて、私が日本で初めて「薬やめる科」を創設した背景には、いくつかの大きな理由があった。
そのうちの1つが「基準値が病気をつくる」という考え方である。
それがどういうロジックなのか、まずは高齢になるにつれて顕著に患者が増えていく“高血圧”を例に挙げて解説してみよう。

“高血圧”の基準値は、日本高血圧学会や厚生労働省によって段階的に引き下げられてきた。
1960〜70年代頃には「年齢+90くらい」とされていたのが、87年になると「上が180、下が100くらい」と引き下げられた。
このとき患者数は少し増えたが、一気に増えたのは99年のこと。
この年、日本高血圧学会が「上が140、下が90を超えれば高血圧」とまたも基準値を下げたことで、推定患者数は一気に約9倍にまで激増。
それ以前には正常範囲内だった人が、基準値が下げられるごとに“異常”とされ、患者数が増えていったのである。
もちろん異常とされた本人は何も変わっていない。
しかもその後もさらに基準値は下げられ、最近では「130を超えたら高血圧」などと宣伝する“健康茶”も売り出されている。
こうして結果的に、3000万人から4000万人もが“高血圧”となってしまった。
ここで国立循環器病センターと厚生省(現・厚生労働省)が1992年に行った研究の結果を紹介しよう。

70歳以上の2000人に対して、1つは本当の降圧薬であるカルシウム拮抗薬、1つは偽薬(プラシーボ) を飲ませて3年間にわたって健康状態を観察した。
すると降圧薬を飲んだ群では8人、偽薬の群では5人が脳梗塞を発症した。
また降圧薬の群は9人、偽薬の群は2人がガンを発症したという。
食生活の改善などによって血圧が自然と下がるのならいいが、薬を使って不自然に数値を下げようとすると、体に色々な影響を与えてしまう…これが真実なのである。
降圧薬としていちばん使われているカルシウム拮抗薬の説明書には、副作用として頭痛、のぼせ、勃起不全、筋肉痛、歯茎が腫れるといった、さまざまな症状がきちんと書かれている。
しかしこうした副作用をすべて納得した上で降圧薬を飲んでいる人はほとんどいないだろう。
またある研究では、沖縄で自立して畑を耕したりしている100歳以上の高齢者の血圧を調べたところ、ほとんどの人が200を超えていたという。
高齢になるにしたがって血管が硬くなるので、その分、圧を上げなければ体の隅々まで血液が巡らなくなってくる。
昔の「年齢+90」という基準値は、確かに理に適ったものだったのである。
それではなぜ、基準値はどんどん下げられていったのか。
本来、病気と健康の境目は曖昧で、数値が多少高い、低いからといっても健康的に暮らしている人は多くいる。
ところが基準値で境目を決めることによって、「正常か、異常か」が明確になる。
つまり基準値を動かせば、意図的に病人を増やせてしまうのである。

“高血圧”であると診断されたすべての人に薬が処方されるわけではないが、患者が増えれば当然、治療薬もたくさん売れるようになる。
今、降圧薬は1兆円規模のビッグマーケットになっている。
薬が売れて得をするのは、誰だろうか。
大騒動になった「ディオバン事件」の経緯をみれば、その理由は推して知るべしである。
次に、健康診断でよく指摘される「悪玉コレステロール値が高め」について解説していきたい。
食品売り場を見回すと、「コレステロールゼロ」や「コレステロール値を下げる」などと謳った商品がたくさん陳列されている。
また健康診断でコレステロール値が高かったことを受けて、医師から「このままだと動脈硬化になるリスクが高まって、心筋梗塞や脳卒中になりやすいですよ」などと言われ、コレステロール値を下げる薬を処方された人もいるはず。
このような、コレステロールを悪者扱いする風潮と不安を煽る医者の言葉とが相まって、コレステロールについて良い印象をもっている人はあまりいないのだろう。
しかしこのネガティブなイメージは、完全な“刷り込み”である。
しかも患者だけでなく、医者もそう思い込んでいるのだから始末が悪い。

そもそも、コレステロールは細胞膜を作るために欠かせない材料であり、もしも足りなくなれば細胞が壊れやすくなってしまう。
ステロイドホルモン(女性ホルモン、男性ホルモン、副腎皮質ホルモン)の材料でもあるので、コレステロール値が低くなるとどんどん老け込んでいく。
また「善玉」とされるHDLコレステロールは、主に肝臓で作られた新しいコレステロールを全身に運ぶ役割を担っている。
一方の「悪玉」とされるLDLコレステロールには、傷んでしまった細胞に新鮮なコレステロールを運んで修復する役目がある。
ただ単に役割が違うだけのことである。
ほかにも、体内にあるコレステロールのうちある程度が脳内にあり、それらは脳からの情報を全身に伝えるのに欠かせない。
脂質の消化・吸収を助ける胆汁酸の材料でもあるなど、私たちが生きていく上でとても重要なものなのである。
このようにHDLコレステロールを「善玉」、LDLコレステロールを「悪玉」と呼ぶこと自体が大きな間違いで、あえて言うなら“コレステロールはすべて超善玉”なのだ。
“高コレステロール”にも、前述した“高血圧”と同じように基準値があり、「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」「中性脂肪に含まれるコレステロール」から算出した「総コレステロール」の値が高いと「高コレステロール血症」(いわゆる“高コレステロール”)、またはいずれか1つでも基準値外 (高い/低い)になると「脂質異常症」と診断される。
そして”高血圧”と同様、昔は総コレステロール値が240以上で“異常”だったのに、現在は基準値が220まで下げられてしまった。
この数値が下げられた理由が「心筋梗塞を起こしやすいから」というものだったのだが、日本はもともと欧米と比べて心筋梗塞が少ない国なのだ。
アメリカでは心筋梗塞を起こす人が日本の約3倍もいて、毎年、多くの人が亡くなっている。
そんなアメリカでさえ基準値は日本より60も高い280である。

このことからも分かるように、日本の数値は厳しすぎるのである。
そして“高コレステロール”と診断され、代表的な治療薬として知られる「スタチン」を飲むと、多くの場合、確かに血中コレステロール値は下がる。
しかしほかの薬と同じように副作用もたくさんあり、その中には「筋肉が溶ける」というものも。
筋肉も細胞でできているため、細胞膜の材料となるコレステロールを強制的に減らすことで細胞膜が脆くなり、溶けてしまうのである。
「まれな症状だ」といっても、薬を飲まなければ溶けないのである。
ほかにも健忘症、糖尿病、鬱、蕁麻疹、不眠、脱毛、便秘、かすみ目 …といった副作用が報告されており、これらは加齢による症状と似ているため、患者も医者も「コレステロールの薬が原因である」と気付かないことも多い。
するとその次には、そうした副作用で出た症状を緩和しようとして、別の薬をどんどん追加する。
「筋肉痛がひどいから湿布」「髪が薄くなってきたから発毛剤」「眠れないから睡眠薬」という具合だ。
また「コレステロール値が高い」と聞くと、多くの人は医師に言われるまでもなく「動脈硬化や心筋梗塞になるリスクが高まる」と思うだろう。
しかしそれが単なる思い込みであることは一目瞭然である。
治療薬が爆発的に売れた後も、心筋梗塞が劇的に減ることはなく、むしろ増えていったのだから。
しかもコレステロール値を下げる薬を服用することで、ガンになる可能性すらあるのだ。J-LIT(Japan Lipid Intervention Trial)という、製薬会社が計画して5万人を6年間追った大規模臨床介入試験によると、薬で数値を180くらいまで下げた人たちにガンが急激に増えることがわかった。
その一方で、服薬しても数値が下がりきれずに高めだった人たちにはガンになる人が少なかったのである。
この結果を端的に言うならば、「コレステロール値を下げる薬を飲んだら、ガンが増えた」となる。
それでも皆さんはまだ、薬を飲みたいと思うだろうか?
私は医療機関の数は現状の10分の1程度にまで減らしてもいいと思っている。

さらには高齢者の多くが服用している薬を中止するとかえって体調が良くなるので、薬も結果的に9割は不要になってしまうと考えている。
そうなれば、計算上は40兆円もの医療費を1割程度まで下げることができる。
「自由に生きた方が健康で長生き。医療と薬のお節介は有害ですよ」と、これが私の結論である。
ここで一つ、私が「病院は不要である」と考える根拠のひとつともいうべき実例を紹介しておこう。
夕張市(北海道)が財政破綻したとき、市内では総合病院が閉鎖され、小さな診療所だけが残された。
やがてその診療所に赴任された森田洋之医師が、医療崩壊した夕張市のその後の医療の現場をつぶさにレポートされた。
するとなんと「医療崩壊する前よりも死亡率が下がった」というのである。
医療が原因で病気になったりすることを指して「医原病」と呼ぶ。
私は、その原因はおそらく過剰な薬や手術、検査による身体的な負担と、医者や看護師から「このままほうっておくと、こんな重い病気になるかも知れませんよ」と言われることによる精神的な不安感によるものだろうと考えている。
実際、「アメリカ栄養研究所」の創立者であるゲーリー・ヌル博士は、「アメリカでは年間78万人、日割りすると毎日2000人が医原病によって死亡し、それが死因の1位と なっている」と論文(2004年発 表)で述べているし、別のアメリカの医学ジャーナルの論文でも「正式に認められた薬を正式に認められた量使ったとしても、アメリカでは毎年10万6000人が死亡している」と発表されている。
厳しい言い方をすれば、それだけ多くの人たちを「病院が殺している」のである。

だからこそ私は、すべての医療従事者に「患者さんを不安がらせるのではなく、元気付けてあげるべきだ」と言いたい。
心が不安に支配され病んでしまえば、体も病んで、さらに病気が悪化してしまうのだから。
そして皆さんがこれから病院と付き合うときは、できる限り「必要な時だけ使い、なるべく病院と関わらない」ようにすることをオススメしたい。
もちろん、どうしても辛いときには薬を処方してもらったり、緊急の場合には外科的な処置をしてもらったりする必要もあるだろう。
しかし落ち着いたら、その病院とは極力、長く付き合わないことが大切である。
それはボクシングの“Hit & Away”と同じで、病院も“サッと使ってサッと引く”。
そうすることで、体はもちろん心も金銭面も負担が軽くなるはずだ。
繰り返しお伝えしておりますが、コレステロールに善玉も悪玉もありませんよ。
HDLもLDLも、どちらも人体にとっては、大切なものなのです。
タバコはかつて、万病の薬とされていました。
頭痛、歯痛、関節痛、腹痛、傷、口臭などによいと…煎じて飲んだり、錠剤にもなっていました。
スペインの医師モナルデスは、1577年に出版した本『新大陸での新発見』のなかで、そう書いています。
その説は、なんと2世紀以上も信じられたそうです。
コレステロールの悪玉説も、同じ道を辿るのでしょうか。


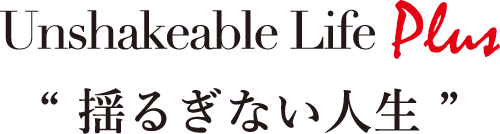 トップへ戻る
トップへ戻る