栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.08.15
わたしたちの消化管には、体内とは思えないほど多様な細菌が共生しています。

とくに小腸から大腸にかけては、細菌が極めて高密度に存在し、腸内細菌叢(マイクロバイオーム)として知られています。
腸内細菌は、食物の分解を助けたり、ビタミンや短鎖脂肪酸などの有用物質を産生したりする一方で、条件が整えば毒素を生産して腸粘膜を損傷し、炎症や吸収障害を引き起こすことがあります。[1]
健康な人の小腸上部には、1mLあたり1万個以下の細菌しか存在しないのが理想とされています。
一方で、大腸(とくに結腸)では1gあたり1000億個以上の細菌が存在し、便の乾燥重量の約半分が細菌成分で占められているともいわれています。[2]

人の消化管は、腸内細菌の過剰な増殖から体を守るために、いくつもの仕組みを備えています。
主な防御機構は以下の通りです。
- 胃酸:強酸性(pH1〜2)の胃液は、大部分の細菌を殺菌します。低胃酸状態では、これらの防御力が著しく低下します。[3]
- 回盲弁(バウヒン弁):大腸内容物が小腸へ逆流しないようにする逆流防止弁です。
- 胆汁と膵液:十二指腸に分泌されるこれらの液には、消化酵素のほかに殺菌力のある成分が含まれています。
- 腸管免疫:腸内の免疫細胞は、外来微生物に対して迅速に反応します。
- 蠕動運動:腸内容物を前方へと送り出し、細菌の滞留と異常繁殖を防ぎます。[4]
これらの防御がうまく働いているときには、腸内細菌は主に結腸に集中しており、小腸や胃ではほとんど繁殖しません。

これは人体のエネルギーを節約しながら細菌の害を最小限に抑える、巧妙な生体戦略といえます。
現代人の食生活では、精製糖質と脂質が多く、食物繊維が圧倒的に不足しています。

このような食事では腸の蠕動が低下し、便秘や腸内容物の滞留が起こりやすくなります。
排便回数が1日に1〜2回未満の人では、結腸に食物残渣が長時間滞留し、細菌が異常増殖するリスクが高まります。[5]
通常、繊維質の多い食事を摂ることで蠕動運動が促進され、24時間以内に食物が消化管を通過し、便として排出されます。
しかし、便秘の人では3日以上排便がないことも珍しくなく、その間に毒素を産生する細菌が腸壁を傷つけることになります。

これにより、水分や栄養素の吸収が妨げられ、慢性的な吸収障害や腸の炎症が引き起こされることがあります。
特に現代の「保存食」や「人工食品」には生きた細菌が少ないため、食物としての安全性はある程度確保されていますが、同時に「生きた食物」を摂取する機会が激減しており、腸内の多様な細菌との健全な共生バランスが失われつつあります。
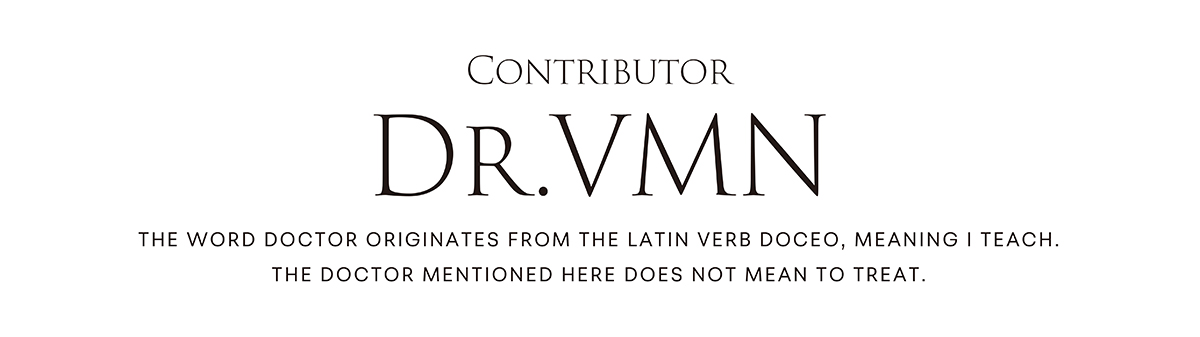
References
1. Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, Finlay BB. Gut microbiota in health and disease. Physiol Rev. 2010;90(3):859–904. — 腸内細菌叢の機能と病理的変化について詳述された総説。細菌の有益な役割と、炎症・吸収障害との関係が述べられています。
2. O’Hara AM, Shanahan F. The gut flora as a forgotten organ. EMBO Rep. 2006;7(7):688–693. — 大腸内の細菌量や便の構成成分に関する記述があり、腸内フローラの重要性を論じた論文。
3. Feldman M, Cryer B, McArthur KE, Huet BA, Lee E. Effects of aging and gastritis on gastric acid and pepsin secretion in humans: a prospective study. Gastroenterology. 1996;110(4):1043–1052. — 胃酸分泌とその防御機能に関する研究。加齢や胃炎に伴う低胃酸状態についても論じています。
4. Furness JB. The enteric nervous system and neurogastroenterology. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;9(5):286–294. — 腸の蠕動運動と腸内環境の調節について、神経系の関与も含めて解説。
5. Burkitt DP, Walker AR, Painter NS. Dietary fiber and disease. JAMA. 1974;229(8):1068–1074. — 食物繊維の摂取と便通・便秘の予防との関連を示した古典的研究。現代食の繊維不足が腸内環境に及ぼす影響についても触れられています。
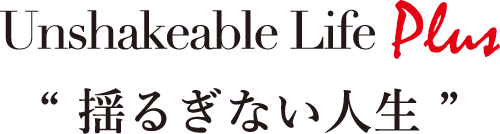 トップへ戻る
トップへ戻る