栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.08.08
消化性潰瘍の形成には、タンパク質不足が大きな要因となる可能性があります。

なぜなら、通常、食事に含まれるタンパク質が胃液(胃酸やペプシンなど)と結合することで、胃酸の過剰な粘膜接触が抑制され、胃粘膜が保護されるからです。
タンパク質が不足すると、胃酸が食物と結合せずに遊離した状態で胃壁や十二指腸壁を刺激し、炎症や潰瘍を引き起こしやすくなります。[1]

また、現代の精製食品中心の食生活では、糖質や脂質は豊富に摂取されている一方で、良質なタンパク質の摂取が不十分であることも多く、胃酸のバランスや消化機能に悪影響を及ぼしています。
私たち人類の祖先は、進化の大部分を狩猟採集民として暮らしながら、「新鮮で生きた食物」を少量ずつ頻回に摂取するという食生活に適応してきました。

野草や果実、昆虫、小動物などの食物を、こまめに摂取しながら移動していたのです。
このような「間欠的かつ自然な食物摂取」は、胃腸に負担をかけにくく、胃酸や消化酵素の分泌が適切にコントロールされていたと考えられます。[2]
やがて農耕や加熱調理が一般化し、定時に三食を摂るという食習慣が定着しました。
この変化によって、食事の「時間」や「形式」が人為的に制限されるようになり、食物は「加熱して食べるもの」「保存できるもの」へと姿を変えていきました。

その結果、少量を頻回に食べるという進化的に適した摂食パターンは失われていったのです。
仕事や家事などが多忙な現代の生活では、「1日1食」や「空腹を我慢してまとめて食べる」など、極端な摂食スタイルが珍しくなくなっています。

このような不規則で極端な食事スタイルは、胃に食物が入ってこない時間が長く、胃酸だけが分泌されて胃粘膜を刺激し、潰瘍形成のリスクを高めます。
一方で、「食事の質」にも大きな問題があります。
精製された糖質中心の食事では、胃酸と結合するタンパク質が少なく、結果的に胃酸が中和されずに粘膜を傷つけてしまいます。

また、ソフトドリンクや清涼飲料などに含まれる酸性成分も、胃酸と同様に消化管への酸性ストレスを増大させる要因になります。[3]
このような食習慣の変化が、現代における胃や十二指腸のトラブル、ひいては消化性潰瘍の増加に直結しているのです。
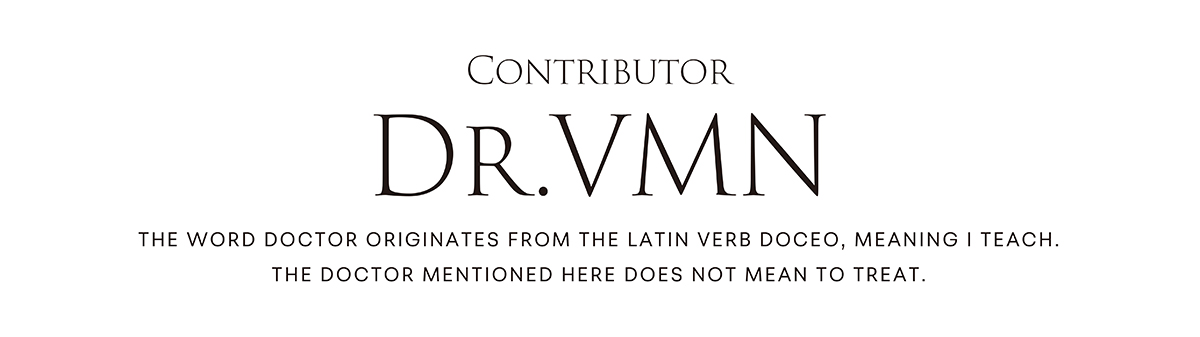
References
1. Fallon S, Enig MG. Nourishing Traditions: The Cookbook that Challenges Politically Correct Nutrition and the Diet Dictocrats. NewTrends Publishing; 2001. — 本書では、伝統的な食文化におけるタンパク質と胃酸の関係について記述されており、タンパク質の不足が胃酸の遊離を招くことが説明されています。
2. Eaton SB, Konner M. Paleolithic Nutrition — A Consideration of Its Nature and Current Implications. New England Journal of Medicine. 1985;312(5):283–289. — 狩猟採集民の食生活と進化的適応についての古典的研究論文。
3. Cordain L, Eaton SB, Sebastian A, et al. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. Am J Clin Nutr. 2005;81(2):341–354. — 現代食と過去の人類食の比較、およびその健康影響に関する詳細なレビュー論文。
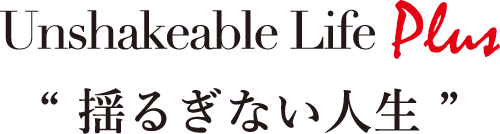 トップへ戻る
トップへ戻る