栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.07.18
世界全体の死亡原因の約70~74%を占める慢性病・生活習慣病は、予防可能でありながら、依然として最大の死因であり、公衆衛生の重要課題です。

世界保健機関(WHO)によれば、2023年の年間の死者数、約5,600万人のうち約4,100万人(全体の74%)が非感染性疾患(NCDs / Non-Communicable Diseases)によるもので、その内訳は以下の通りです。
※その他、高血圧、脂質異常症、肥満、慢性腎疾患、認知症などもNCDに含まれ、日本では、NCD=生活習慣病と表現されることも多くあります。
「生活習慣病(慢性病)」は、食事、運動、飲酒、喫煙、睡眠、ストレスなどの生活習慣が深く関わるNCDの一部です。

前述の通り、その多くが予防可能(約80%以上は食事・運動・禁煙などでリスクを下げられる)でありながら、高齢者だけでなく、40歳未満の若年層の死亡も年々増加傾向を示しており、世界中で医療費・労働力損失の主因となっています。
全世界で最も優れた調査機関であるアメリカ上院に設置された「上院栄養問題特別委員会(U.S. Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs)」は、国内外の研究者や医療機関と連携し、世界各国の食生活と健康の関係について大規模かつ多角的な調査を行いました。
その成果として、一九七七年には全5,000ページを超える膨大なレポート『栄養と健康に関する特別報告書(Dietary Goals for the United States)』が発表されています。
この報告書は、当時のアメリカをはじめとする先進諸国の食生活が、慢性疾患や生活習慣病の増加と深く関係していることを厳しく指摘し、日本の食習慣についても見直しの必要性を訴えています。
医学・栄養学・科学などの世界最高峰の叡智を集めた委員会の濃密な審議調査の結論として、重要な提言がいくつか提出されましたが、その中でもっとも重要なものの一つが以下の内容です。
ガン、心臓病、脳卒中などアメリカの6大死因となっている病気は、現代の間違った食生活が原因になって起こる「食原病」である。
この間違った食生活を改めることで、これらの病気を予防する意外に先進国民が健康になる方法はない〞。
そして、医師の再教育の必要性も強く訴えています。
つまり、現代の〝万病は腸にはじまる〞のです。
そしてその多くの原因が「便秘」であり、便秘によって動物性タンパク質が腐敗した「酸性腐敗便」、さらには腐敗便が引き起こす「有害物質」とその「全身循環」、「酸性ストレス」、「炎症体質」という悪循環だというのが、弊社の見解です。
心当たりのある方は、この悪循環から早急に抜け出す必要があります。
まずは「緩下剤」を使って、体に排泄する習慣をつけさせることが肝要ですが、これは対症療法で、便秘という病気が根治するわけではありません。
では、その先はどうすればいいのでしょうか?
実は、消化管に引き起こされる障害には、栄養が深く関わっているのです。
ということで本稿は、健全な消化管機能を取り戻すことを目的に、消化管障害と栄養療法の関連について、読みやすように短編のシリーズでお送りします。

消化管は、単一の管から発達してきた器官であり、構造や機能の面で高度に専門化しています。
その主な役割は、食物の受け入れ、消化、吸収、そして不要物の排泄にあります。
消化管は口腔から始まり、咀嚼や唾液分泌によって消化の第一段階が行われます。
その後、食道を通って胃へ送られ、さらに小腸・大腸・直腸を経て、最終的に肛門から排出されます。
この一連の流れは、あたかも個別の臓器のように扱われがちですが、実際には消化管全体が一つの統合された器官であり、臨床的にも統一的に評価・治療されるべきものです。
たとえば、胃に病変がある場合でも、その他の消化管が完全に健康であるとは言い切れません。

むしろ、消化管のある部分に異常が現れているということは、全体の機能不全の表れである可能性が高いと考えられます。
実際、口腔内の健康状態、たとえば歯茎の腫れや歯の脱灰、舌の苔などは、しばしば全身状態や消化管の健康状態を反映しています。
近年では、歯周病と糖尿病や心血管疾患、腸内環境の悪化との関連も報告されており、歯科医が患者の全身状態を見抜く重要な立場にあることが明らかになってきています。[1・2]
消化管には、管の内側あるいは外側に「付属腺」と呼ばれる複数の分泌器官が存在します。
唾液腺は口腔内に唾液を分泌し、胃腺は塩酸やペプシンを分泌します。
膵臓は膵液に含まれる多数の消化酵素を小腸へ分泌し、肝臓は胆汁を生成して胆嚢に貯蔵し、必要に応じて十二指腸に分泌します。
腸管自体も粘液や消化酵素を分泌する腸腺を備えており、これらの全体が協調して消化と吸収を支えているのです。[3]
このように、消化管の主な機能が食物の消化と栄養素の吸収にあることを考えれば、消化管の不調の多くが食生活と深く関わっていることは自然なことです。
潰瘍性疾患、大腸炎、虫垂炎、糖尿病、肥満、さらには大腸癌や膵疾患まで、多くの消化器系疾患が、現代人の低食物繊維・高糖質・高脂肪の食事に対する反応として発症しています。
これらは「糖質代謝異常症候群(metabolic syndrome)」の一部として位置づけられる病態でもあります。[4・5]

とくに欧米型の高カロリー・低繊維食に起因する消化器疾患の例は、以下のように分類されます。
• 口腔:歯周病、齲蝕(虫歯)[6]
• 胃:胃潰瘍、胃食道逆流症(GERD)、食道裂孔ヘルニア[7]
• 小腸・大腸:便秘、潰瘍性大腸炎、クローン病、虫垂炎、大腸癌、下痢、ビタミン欠乏症[8・9]
• 直腸:直腸癌、痔核(痔)[10]
付属腺
• 膵臓:膵炎、膵がん、膵β細胞の破壊によるインスリン分泌不全(2型糖尿病)[11]
• 肝臓・胆嚢:脂肪肝、胆石、胆嚢炎[12]
これらの疾患はすべて、食事内容、腸内細菌叢、消化管バリア機能、炎症性サイトカインの活性化、ミトコンドリア機能の低下などと密接に関連しています。
栄養療法の観点からは、特定の栄養素(ビタミンD、オメガ3脂肪酸、プレバイオティクス、抗酸化物質など)によって消化管の恒常性維持を図ることが、予防および補助療法として有効であることが多くの研究から示唆されています。[13・14]
さあ次週から「どうやって消化管障害を根治させるのか?」その具体策を、栄養療法の観点からみていきましょう!
To be continued next week
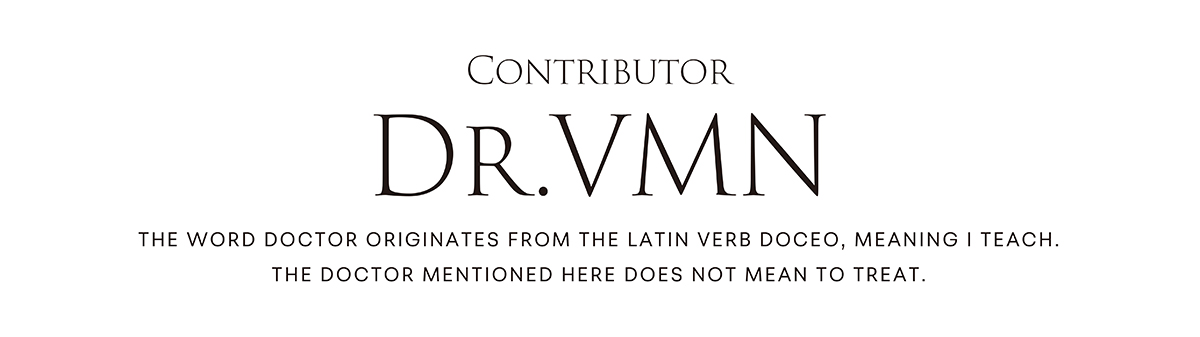
References
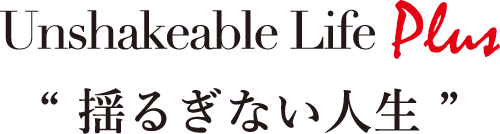 トップへ戻る
トップへ戻る