栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.07.11
アスコルビン酸(ビタミンC)は、一般的には錠剤やカプセル、水に溶かした粉末などの形で経口摂取されます。
医師の管理下では、アスコルビン酸を静脈内に直接注射することもありますが、日常的な摂取としては、経口での服用が最も一般的かつシンプルな方法です。

市販されている錠剤やカプセルの含有量は100〜1000mgと幅がありますが、500mgが最も一般的な規格です。
特に高用量で使用する場合には、粉末状のアスコルビン酸(結晶)が実用的でコストパフォーマンスにも優れています。
なお、ビタミンC製品には、本来必要のない添加物(砂糖、でん粉、着色料、香料など)が含まれていないものを選ぶのが望ましいです。
保管については、直射日光や高温を避けた、適度に乾燥した場所が適しています。
冷蔵庫内は湿度が高く冷えすぎるため避け、一般的な戸棚などを利用するとよいでしょう。
粉末のアスコルビン酸を水に溶かすと、すぐに酸化が始まります。
ジュースに溶かした場合はさらに酸化の進行が早くなりますので、溶液はできるだけ早めに飲み切るのが理想的です。
また、徐放型(時間をかけて徐々に放出されるタイプ)のビタミンC製剤は、血中濃度を比較的安定して維持し、尿中への排出も抑える効果があります。
ただし、価格が高めであるうえに、一部の製剤は特に高齢者において溶けにくく、吸収されにくいこともあります。
病気の治療を目的とする場合には、血中のアスコルビン酸濃度を一気に高めることが重要となります。
そのため、初期には高用量で投与することが理想的とされています。
アスコルビン酸は弱い有機酸であり、通常の胃酸のレベルに大きな影響を与えることはありませんが、酸味に敏感な人にとっては飲みにくい場合があります。
そのようなときは、炭酸水素ナトリウム(重曹)や炭酸水素カリウムを少量加えて中和することで、酸味を軽減できます。
ナトリウムの摂取量は多少増えますが、アスコルビン酸とともに体外へ排出されるため、通常の範囲であれば問題は少ないと考えられます。

また、経口摂取ではなく、点滴や注射として投与する場合には、ナトリウムやカルシウムと結合させたアスコルビン酸塩(アスコルビン酸ナトリウムやアスコルビン酸カルシウム)が用いられます。
では、どれくらいの量が治療的に効果的なのでしょうか。
クレンナー医師は、最大で1日30万mg(300g)までの投与を行ったと報告しています。
彼が一般に使用していたのは、体重1kgあたり350〜700mgという水準で、これは現代の基準でも非常に高用量に相当します。
しかし、まさにこの「大量投与」によってこそ、クレンナー医師は数々の臨床成果を挙げることができたのです。
彼は繰り返し「少量では効かない」と強調し、次のように述べています。
「本当に結果を求めるのなら、十分量のアスコルビン酸を使いなさい」
オーソモレキュラー療法の実践者が推奨するビタミンCの最適用量は、果たして危険なのでしょうか。
結論から申し上げますと、ビタミンCは高用量であっても、非常に安全性の高い栄養素です。
ただし、どんなものであっても摂りすぎれば、程度の差こそあれ、身体に不快な反応を引き起こすことはあります。
「毒性」という言葉は、まるで即座に生命の危険があるような印象を与えるかもしれませんが、ビタミンCの副作用は極めて軽微で、危険と呼べるようなものではありません。
仮に摂り過ぎた場合でも、重篤な症状が出る前に体は警告サインを発します。
最も一般的な反応は「吐き気」や「お腹がゆるくなる」ことです。
これは多くのビタミンに共通する特徴であり、自然と服用量を控えるようになります。

特にアスコルビン酸に関しては、過剰摂取の初期症状として下痢が起こることが知られており、これは安全限界を知らせるわかりやすい指標になります。
米国中毒情報センター協会(AAPCC)のデータによると、アメリカ国内でビタミンCによる死亡例は年間ゼロ件です。
ところが、ビタミンを否定的に捉える論者はこのような統計には触れようとせず、科学的な正確さを欠いた批判を行うことがあります。
実際、市販の一般的な処方薬と比べると、ビタミンCの副作用は事実上ほとんど存在しないと言ってよいでしょう。
ここ10年ほどの間に、「ビタミンCの高用量摂取は腎結石の原因になる」という説が定着したように見えます。
特に、ビタミンの代謝について深く学んでいない一部の医師の間では、この考え方が根強く残っています。
しかしこの主張は、あくまで理論上の可能性にすぎず、現実には科学的な裏づけに欠けています。
実際には、ビタミンCには結石の形成を抑え、むしろ溶解を助ける作用があることが示されています。(1)
ロバート・F・キャスカート三世医学博士は、1969年からビタミンCの大量投与を始め、これまで2万5,000人以上の患者に処方してきたと述べていますが、その中に腎結石を発症した例は一人もいないと報告しています。(2)
また、フレデリック・クレンナー医師も、アスコルビン酸が腎結石の原因になるという主張は「迷信にすぎない」と述べており、近年の研究によってもこの見解が支持されています。(3)

1974年には、ビタミンCを食事に加えた際に、摂氏37度で30分間保温すると、食品中のビタミンB12が破壊されたという試験管レベルの研究報告がありました。
この報告を基に、著者らは「風邪予防の目的で使われている高用量のビタミンCは、食物と一緒に摂取されるとビタミンB12を破壊する可能性がある」と結論づけました。(4)
しかし、この研究には複数の問題がありました。
まず、ビタミンB12の測定方法自体が不正確であり、さらに試験管内での観察結果をそのまま臨床にあてはめていた点です。
この研究はJAMA(米国医師会雑誌)に掲載されましたが、それに対する批判的な意見は掲載されずに却下されました。
ところが2年後、別の研究グループがより正確な分析手法で再検証を行ったところ、ビタミンB12の喪失は確認されませんでした。
しかも、当初の研究の20倍量のアスコルビン酸を用いても、ビタミンB12は破壊されなかったのです。(5)
臨床的な観点からも、この懸念は事実と矛盾しています。
現在、高用量のアスコルビン酸を継続的に摂取している人は全世界で何百万人と存在していますが、ビタミンB12欠乏による悪性貧血を発症した事例は報告されていません。(6)
ビタミンCにはこれまでにも多くの「有害性」に関する主張がなされてきましたが、それらは深刻なものとは言いがたく、多くは理論上の懸念や、根拠の乏しい憶測に基づくものです。
たとえば、アスコルビン酸は流産の原因になる可能性があるという説があります。
しかし、これを裏づける臨床報告は存在しておりません。
もし仮に、ビタミンCの摂取によって流産が起きたと医師が確信できるような事例があったならば、即座に症例報告として学術誌に掲載されていたことでしょう。
実際には、クレンナー医師は日常的に数百人規模の妊婦にビタミンCの大量投与を行っており、そこでは観察されたのは流産ではなく、母子ともに健康上の恩恵でした。
彼の産科において流産例はなく、むしろ安全かつ楽なお産が促され、生まれた子どもたちは皆、非常に健康的だったため、看護師たちはその子どもたちを「ビタミンCベイビーズ」と呼んでいたほどです。

また、ビタミンCが「ガンを促進する」との主張も見受けられます。
ある試験管内の研究では、2000mgのビタミンCが脂肪酸とヒトDNAに影響を及ぼす可能性があると示されました。
しかし、この用量で有害作用があるのであれば、わたしたちの近縁種である他の霊長類や、体内で1日あたり2,000〜10,000mgのビタミンCを自然に合成している多くの動物は、すでに進化の過程で淘汰されていてもおかしくありません。
実際には、多くの適切に設計された研究が示している通り、高用量のビタミンCは、ガン患者の生活の質や余命の延長に寄与しています。(7)
抗ガン剤治療においても、ビタミンCの大量投与によって、吐き気や脱毛といった副作用が軽減され、医師がより積極的な治療を行いやすくなることが知られています。
ところが、ある種の勢力にとって、新しい治療法が既存の「確立された」治療法に取って代わることは都合が悪いため、「毒性がある」という証拠を探し出そうとする傾向があります。
化学療法に代表されるような、明らかな副作用を持つ治療法があっても、その問題点は十分に取り上げられない一方で、ビタミンCのような代替的手段に対しては必要以上に厳しい批判が加えられるというのは、よくある構図です。
また、「大量に摂取していたアスコルビン酸を急にやめると、リバウンド現象によって以前よりも健康を害する」といった主張もあります。
これも、一つの乳児研究に基づくものであり、ビタミンCを摂取していた母親から生まれた乳児が、生後しばらくしてビタミン不足に陥ったとされるものです。
しかしながら、この研究から実際に読み取れるのは、「ビタミンCを摂っていると元気である」という事実のほうです。
アスコルビン酸を摂取している人が突然服用を中断すれば、以前より体調が悪くなったように感じるのは当然とも言えます。

特にガン患者など、高用量のビタミンCを治療の一環として摂取している場合には、急な中断は避けるべきです。
なぜなら、ガンの再発や進行のリスクが高まることが研究で示されているからです。
体調が安定している人であっても、ビタミンCの服用を続けることでウイルスや細菌への防御力が高まり、不調の予防に役立ちます。医療者や医療機関が、偏見や無理解からビタミンCの使用を制限するようなことがあってはなりません。
そのような場合には、その影響に対する責任が問われるべきです。
あらためて強調しますが、アスコルビン酸の最適な摂取量とは、「お腹がゆるくならない程度の量」です。
このポイントを知らなければ、医師も患者も、下痢や腹部膨満といった副反応を過剰に恐れてしまうことになりかねません。
アスコルビン酸には、むしろ緩下剤としての機能があり、その作用の強さは用量に比例します。
まれに、アスコルビン酸に対して過敏な反応を示す人もいますが、それはビタミンそのものではなく、錠剤に含まれる添加物(賦形剤)によるアレルギー反応である可能性が高いです。
進化的に見ても、必須栄養素であるビタミンCそのものに対してアレルギー反応を起こすというのは不自然です。
万一そのようなことが起きるのであれば、はるか昔に生存が困難になっていたでしょう。
我々が考慮すべきは、ビタミンCが有用か否かではなく、「どのような状況で、どのくらいの量が必要か」という点にあります。

ビタミンC(アスコルビン酸)は、グルコースと似た構造を持ち、かつて多くの動物が体内で合成していましたが、人類を含む一部の種ではこの能力を喪失しました。
その背景には、食物から十分なビタミンCを摂取できる環境があったこと、そして合成に必要なエネルギーを他に回せるという進化的利点があったと考えられています。
体内では、副腎・白血球・目・脳などさまざまな組織で高濃度に存在し、ホルモン合成、免疫機能、抗酸化作用、ヒスタミンの分解、コラーゲン生成など、生命維持に欠かせない働きを担っています。
ビタミンCは、風邪、肺炎、ガン、動脈硬化、糖尿病、ウイルス・細菌感染症など、30以上の疾患に対する予防・治療効果が報告されています。
特に高用量のビタミンCは、ガン患者のQOL改善や抗ガン剤の副作用軽減に有効であり、動脈硬化や心筋梗塞の予防にも役立つとされています。
また、風邪やインフルエンザの発症頻度・重症度・持続期間を有意に減少させるという多くの臨床試験結果が示されており、高用量での使用がカギとなります。
化学的・物理的・心理的ストレスが体内のビタミンCを急激に消費するため、発熱、外傷、放射線曝露、重金属中毒、毒素(蛇毒・細菌毒)などへの対応には高用量投与が求められます。
アスコルビン酸は毒素の解毒、免疫強化、抗酸化などを通じてストレス反応を緩和し、身体を保護します。
ビタミンCの安全性については、数十万mgの投与でも致死性の副作用は報告されておらず、副作用として最も多いのは一過性の下痢程度です。
腎結石や悪性貧血などの懸念は、過去の不正確な研究や理論的な推測に過ぎず、近年の研究では否定されています。
また、「万能であるがゆえに信用されない」という逆説的な状況も指摘されています。
製薬業界で多用途な薬は称賛される一方で、ビタミンCのような栄養素が複数の病態に効くと「疑わしい」と見なされてしまう現状には、ダブルスタンダードの存在が否定できません。
経口での摂取が最も一般的で、病態や目的に応じて粉末、錠剤、カプセル、徐放製剤などを使い分けます。
静脈内投与は、特に重篤な症状や高用量が必要な場合に用いられます。
最適量は個人差があり、一般的には「下痢を起こさない範囲の最大量」が推奨されます。
クレンナー医師やキャスカート医師の臨床経験では、1日10〜30g以上が用いられることもありました。
いずれの場合も、症状や目的に応じて柔軟に調整することが重要です。
ビタミンCは、妊娠中の健康維持やお産の質の向上、SIDS(乳幼児突然死症候群)の予防、皮膚線条(妊娠線)予防、ヘロイン依存症の離脱補助など、幅広い分野で応用されています。
また、アレルギー性疾患やヒスタミン反応への対応にも有効であるとされ、薬理作用と栄養作用の両面を持つ「十徳ナイフ」のような存在といえます。
ビタミンCは、多くの現代病に対する防御と回復を助ける、極めて安全かつ汎用性の高い栄養素です。
それにもかかわらず、科学的根拠の薄い批判や誤情報によって過小評価されがちです。
オーソモレキュラー療法では、ビタミンCの適正使用こそが、現代医学が抱える限界を補完し、真の健康維持に貢献すると位置づけています。

ビタミンCは、あまりにも多目的に使えるがゆえに、かえって誤解や敬遠の対象となっている節があります。
フレデリック・R・クレンナー医学博士は、アスコルビン酸(ビタミンC)が、抗毒素、抗菌薬、抗ウイルス薬として非常に幅広く有効であることを、臨床を通じて実証しました。ポリオ(急性灰白髄炎)、肺炎、麻疹、連鎖球菌感染症、蛇咬症、ロッキー山紅斑熱など、さまざまな疾患に対してビタミンCが効果を示したのです。
こう聞くと、「たった一つの栄養素がそんなに多くの病気に効くなんて本当なのか」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、クレンナー医師が効果を報告した疾患はこれだけにとどまらず、さらに50種類近くにおよんでいます。
これに対して、医師だけでなく患者自身も、主体的にその治療と回復のために取り組んできました。
このような状況を一言で説明するならば、「一つの栄養素でこれほど多くの病気が治るのは、一つの栄養素の欠乏が、これほど多くの病気を引き起こしているからである」と言えるでしょう。
ここには、ビタミンCの評価が不当に低く見積もられてしまうもう一つの理由もあります。
それは「宣伝の問題」です。
製薬会社が開発する薬剤が多目的に効くとなれば、「薬効が広い」「魔法の薬」ともてはやされます。
ところが、ビタミンや栄養素が同じように幅広く作用すると、「一時的なブーム」「効果をこじつけている」といった否定的な評価を受けがちです。
こうしたダブルスタンダード(御都合主義)については、より多くの人にその存在を知ってもらい、疑問を持ってもらう必要があるでしょう。
ビタミンCは薬のように作用しますが、薬がビタミンCのように作用することはありません。
たとえば、注意欠陥多動性障害(ADHD)はリタリン®(メチルフェニデート)不足で起こるわけではありませんし、関節炎はアスピリン不足によるものでもありません。
けれども、こうした疾患に見える多くの健康問題は、実は栄養素の不足、つまり「ありふれた栄養欠乏」によって引き起こされている可能性があるのです。
この考えに基づいて治療を行った1949年当時のクレンナー医師の取り組みは革新的でしたが、今なおその発想は新鮮であり、実践される価値があるといえるでしょう。

ビタミンCの大量投与療法が有効で安全であるということは、すでに多くの文献で報告されているにもかかわらず、「ビタミンCは抗菌薬として最も広範な作用を持ち、抗ヒスタミン薬、抗毒素、抗ウイルス薬としても優れている」と理解している人は、決して多くはありません。
さらに残念なことに、一般の人々だけでなく、多くの医師、そしてほぼすべてのマスコミが「ビタミンCは効かないどころか危険である」と信じてしまっているのです。
アスコルビン酸は、まさに十徳ナイフのような多用途な栄養素です。
ところが、これほど多くの効果を持っているという事実自体が、「かえって信じがたい」といった先入観によって不当に扱われてきました。
しかし、わたしたちの体は数十兆個の細胞から成り、数千にも及ぶ生化学反応を、たった十数種類のビタミンで維持しているのです。
ビタミンC一つに多くの働きがあることは、むしろ当然といえるのではないでしょうか。
生命は、人智を超えた複雑な機構によって機能しています。
このシステムを動かしているのが、本来の「薬」である「栄養素」なのです。
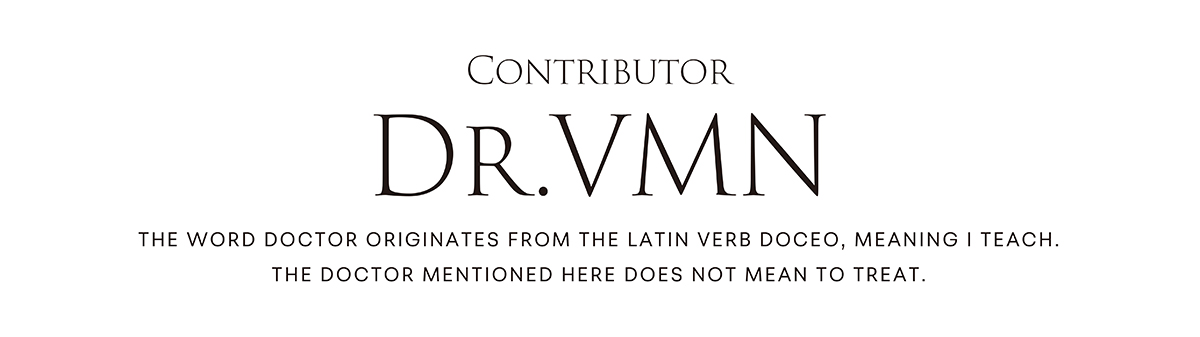
References
(1) McCormick. “Lithogenesis and Hypovitaminosis.”
(2) Cathcart R.F. Available online at: www.orthomed.com index2.htm. (See comment near bottom.
of webpage.)
(3) Gerster, H. “No Contribution of Ascorbic Acid to Renal Calcium Oxalate Stones,” ,Ann Nutr Metab 41:5 (1997): 269-282. See also: Hickey. S., and H. Roberts. “Vitamin C Does Not Cause Kidney Stones.” Orthomolecular Medicine News Service (July 5, 2005). Available online an http: orthomolecular.org/resourcesomns/v01n07.shtml.
(4) Herbert, V., and E. Jacob. “Destruction of Vitamin B1; by Ascorbic Acid.” 7,43/4 230 (1974): 241-242.
(5) Newmark, H.L., J. Schemer, M. Marcus, et al. “Stability of Vitamin B12 in the Presence oi Ascorbic Acid.” Am J Clin Nutr 29 (1976): 645-649.
(6) Marcus, M, M. Prabhudesai, and S. Wassef. “Stability of Vitamin B1? in the Presence of Ascorbic Acid in Food and Serum: Restoration by Cyanide of Apparent Loss.” Am J Clin Nutr 33 (1980): 137-143. Hogenkamp, H.P.C. “The Interaction between Vitamin B12 and Vitamin C.” Am J Clin Nutr 33 (1980): 1-3.
(7) Murata, Morishige. and Yamaguchi. ‘Prolongation of Survival Times of Terminal Cancer Patients by Administration of Large Doses of Ascorbate. “Also: Hanck. A. (ed.). Vitamin C: New Clinical Applications. Bern: Huber. 1982, pp. 103-113. Null. G„ H. Robins, M. Tanenbaum, et al. “Vitamin C and the Treatment of Cancer: Abstracts and Commentary from the Scientific Literature.” Townsend Letter for Doctors and Patients (April/May 1997), Riordan. N.H.. et al. “Intravenous Ascorbate as a Tumor Cytotoxic Chemotherapeutic Agent.” Med Hypotheses 44:3 (March 1995): 207-213. Rivers, J.M. “Safety of High-level Vitamin C Ingestion. Third Conference on Vitamin C.” Ann NY Acad Sci 498 (1987).
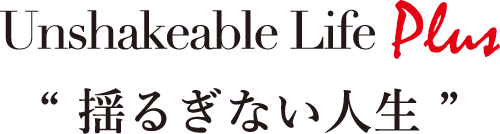 トップへ戻る
トップへ戻る