栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.07.04
目次
古典的な壊血病は、現代の先進国ではきわめてまれな疾患とされています。そのため、仮に壊血病を発症していたとしても、実際には診断されないまま見過ごされることが多いのが現状です。ただし、この病気に対する唯一かつ確実な治療法は、できるだけ早くアスコルビン酸(ビタミンC)を投与することにあります。

症状の緩和や明らかな徴候を取り除くことが目的であれば、それほど多量のビタミンCは必要ないかもしれませんが、「健康を回復させる」ことを目的とするのであれば、1日数g単位の摂取が必要になる可能性があります。
一方、「潜在的壊血病(サブクリニカル・スコルバート)」は古典的な壊血病よりもはるかに頻度が高いと考えられています。しかしながら、こちらもまた正しく診断されることは極めてまれです。その背景には、医師側における潜在的壊血病の鑑別診断に関するトレーニングや知識が不十分であるという問題があります。
多くの医師にとって、歯ぐきからの出血といった典型的な症状が出ていない限り、「アスコルビン酸が必要かもしれない」という発想にすら至らないのが実情です。潜在的壊血病に関しては、診断を確定できるような採血検査も存在しません。
したがって、臨床では食事歴の問診が非常に重要となります。アスコルビン酸を多く含む食材――たとえば新鮮な果物や野菜――をほとんど摂取していない場合、また、心理的あるいは身体的なストレスが大きくかかっている場合、そして明確な病名がつかないにもかかわらず壊血病の初期症状に似た不調が見られる場合には、潜在的壊血病の可能性を強く疑う必要があります。

アスコルビン酸(ビタミンC)は、ストレスに対処するうえで、おそらく体内で最も重要な化学物質の一つです。動物はストレスを受けると、体内でのアスコルビン酸の合成を増やします。白血球は、損傷した組織へアスコルビン酸を運び、高濃度に集中させますが、これは血流による単なる拡散では達成できないレベルです。ストレスがかかると、副腎からアスコルビン酸が奪われ、その酸化も促進されます。(1)
人体がストレスを感じる要因には、化学的、身体的、心理的なものがあります。たとえば、重金属のような有害な無機物質もその一つです。高用量のアスコルビン酸は、モルモットに投与されたシアン化水銀の致死率を下げ、二塩化水銀に対しても生体保護的に作用します。また、水銀系の利尿剤による毒性を軽減し、鉛の毒性も抑えます。実際に、一日わずか100mgのビタミンC摂取で、大規模な工場で鉛中毒に苦しむ労働者の症状が消失したという報告もあります。鉛中毒の症状は、潜在性壊血病に非常に似ています。(2)
さらにアスコルビン酸は、梅毒治療に使われるヒ素系薬剤や、クロム酸塩、金塩(塩化金酸ナトリウム)などの毒性からも体を守る作用があります。歯科用アマルガムに含まれる水銀も体内で害を及ぼす可能性があり、アスコルビン酸はその排出を助けるとされています。
また、アスコルビン酸はベンゼンによる毒性変化を改善し、ベンゼンが体内のビタミンCを急速に消費してしまう現象にも対応します。ラットにベンゼンを注射すると、アスコルビン酸の体内合成が増加することが確認されています。
アスコルビン酸は、マウスをストリキニーネ(神経興奮性の毒)から守り、ジギタリス(強心薬)の副作用やアスピリンの毒性も軽減させます。ビタミンAの過剰摂取で起こる壊血病様の症状も抑えるとされています。バルビタール中毒(中枢神経抑制薬による依存・中毒)にもアスコルビン酸は効果があるとされ、投与が推奨されます。(3)
麻酔もまた強いストレスとなり、血中のアスコルビン酸濃度を低下させます。アスコルビン酸が不足した動物では、麻酔がすぐに効きやすく、かつ覚醒が遅れる傾向が見られます。
もっとも一般的な化学的ストレスの原因には、大気や水の汚染、喫煙が挙げられます。こうした有害要因によるストレスは、大量のアスコルビン酸を摂取することで軽減可能です。アスコルビン酸は強力な抗毒素として、破傷風毒素などの細菌毒も不活化させます。事前にビタミンCを投与された動物では、破傷風の症状が明らかに軽くなったと報告されています。(4)

現在、アスコルビン酸はボツリヌス中毒には用いられていませんが、強い解毒作用を持つことから、高用量での治療が検討されるべきだという意見もあります。また、毒蛇に咬まれた場合の治療にもアスコルビン酸が用いられ、良好な結果を示しています。
身体的ストレスもまた、大量のアスコルビン酸を必要とします。通常、急性のストレスに対しては体内のビタミンCで対処可能ですが、慢性的なストレス下ではさらに多くの補給が必要です。発熱、熱傷、寒冷への曝露、外傷、骨折、高地への移動、放射線被曝なども、アスコルビン酸の需要を増加させます。(5)
実際、白血病の放射線治療を受けた患者の中には、1日約10gのアスコルビン酸を摂取していた例があり、彼らは吐き気をほとんど感じず、脱毛も起きなかったとされています。核爆発によって放出される「死の灰(フォールアウト)」など、環境中の放射性物質への曝露に対しても、ビタミンCの高用量摂取が勧められます。放射線によって体内で発生するフリーラジカルをアスコルビン酸が除去し、細胞損傷を防いでくれるためです。これにビタミンEやセレンを併用すれば、さらに防御効果が高まると考えられます。
極度のストレスがかかると、体内のアスコルビン酸のほとんどが酸化され、デヒドロアスコルビン酸という形になります。健康な組織では、ビタミンCは主にアスコルビン酸の形で存在していますが、この形は細胞膜を通過しにくく、酸化型であるデヒドロアスコルビン酸のほうが膜を通りやすいため、細胞内で還元されて再びアスコルビン酸として機能します。
しかし、強いストレス下では、この還元機構が破綻し、デヒドロアスコルビン酸のまま残ってしまうことが起こります。一般的に、健康な状態とは「酸化が少ない状態」であり、病気の際には体内で過剰な酸化が進んでいると考えられます。こうした背景から、健康を取り戻すにはビタミンCを通常よりも多く補給することが重要になります。
キャスカート医師は、アスコルビン酸を「処方量に上限のないフリーラジカルのスカベンジャー(掃除屋)」と呼んでいます。(6) 実際、大量に摂取することでその役割はさらに強力になります。
酸化ストレスの原因として注目すべきなのは、アレルギー性ストレスを含むストレス全般に関与する生化学反応です。ストレス時にはヒスタミンの放出が増えるとともに、アドレナリン、ノルアドレナリン、コルチコステロイド(副腎皮質ホルモン)などのホルモン分泌も増加します。これらの代謝過程すべてに、アスコルビン酸が関与しています。
たとえばノルアドレナリンやアドレナリンの合成にはアスコルビン酸が不可欠であり、その過程でアスコルビン酸は酸化されてデヒドロアスコルビン酸に変化します。このとき副産物として生成されるアドレノクロムは、通常は無毒なジヒドロキシインドールへと変換されますが、これにもアスコルビン酸の関与が必要です。
また、副腎皮質ホルモン(コルチコステロイド)の合成にもアスコルビン酸が必須であり、これが副腎にビタミンCが大量に蓄えられている理由の一つです。さらに、アスコルビン酸はヒスタミンの分解にも関与しており、虫刺され、毒蛇咬傷、植物毒、アレルギー反応、熱傷などの治療にも効果を発揮します。
このように、アスコルビン酸はストレスに対する多面的な生化学反応において中核的な役割を担っており、ストレスが増すほど酸化も進み、それがビタミンCの需要を高める結果につながります。オーソモレキュラー医学では、アスコルビン酸の補給こそが、こうした病態への適切な介入であるとはっきりと主張されています。

多くの典型的なアレルギー反応は、ヒスタミンの放出によって引き起こされています。体内で過剰に放出されたヒスタミンは、皮膚のかゆみや腫れ(腫脹)、じんましん、紅潮(血管拡張)、そして場合によっては血圧の低下といった症状を誘発します。
一般的に使われている抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンが生体組織に作用するのをブロックし、その効果を遮断することで症状を抑えるものです。しかし、ヒスタミンの働きを軽減する方法はそれだけではありません。たとえば、ナイアシン(ビタミンB3)を大量に摂取することで、体内のヒスタミン貯蔵量を減らすことが可能です。
また、ヒスタミンが放出された後に、それ自体を化学的に破壊する方法もあります。これに有効なのが、アスコルビン酸(ビタミンC)です。試験管内の実験では、アスコルビン酸とヒスタミンが急速に反応し、互いに無力化することが確認されており、この反応は体内でも同様に起きているとする研究結果もあります。
虫刺され、毒蛇咬傷、有毒な植物に触れたときの反応といった、いわゆるヒスタミンが媒介する毒性反応にも、アスコルビン酸は高い効果を発揮します。こうした状況でビタミンCを効果的に用いるには、「高用量で、できるだけ早く」というのが基本原則です。ヒスタミンが放出された直後に投与するほど、その効果は大きくなります。
とはいえ、最も理想的なのは予防的に用いることです。たとえば虫に刺される可能性があることが事前にわかっている場合には、数日前から最適量のビタミンCを摂取しておくのが賢明です。そうすることで、ヒスタミンが過剰に放出されるのを抑え、アレルギー反応の発現や重症化を防ぐことができるでしょう。
ライナス・ポーリング博士が1970年代初頭にビタミンCの大量投与による健康効果を発表して以降、「ビタミンCを摂りすぎると腎結石ができる」という説が、あたかも医学的常識であるかのように語られるようになりました。しかしながら、これは明確に否定されるべき“迷信”であり、科学的根拠に乏しい俗説にすぎません。(7)

この「ビタミンCによる腎結石説」は、いわばユニコーン(空想上の一角獣)のような存在です。多くの人がその名前を知っており、姿を思い浮かべることはできますが、実際に見たことがある人はいませんし、現実には存在しません。「ビタミンCが腎結石を引き起こす」という話もこれと同様で、広く信じられてはいるものの、事実として確認された例は極めてまれです。医師の中にも「そう聞いたことがある」という人は多いものの、自身の臨床でそれを実際に目にしたことがある人はほとんどいません。
実際には、ビタミンCは腎結石を引き起こさないどころか、むしろその予防に役立つ可能性があります。アスコルビン酸は尿量を増やし、尿のpHを低下させることで、カルシウムとシュウ酸が結合して結石を形成するのを防ぐ作用をもっています。こうした特性はすべて、腎結石の形成を防止する方向に働きます。(8)
腎結石の予防および治療にビタミンCを最初に推奨したのは、1946年のマコーミック医師でした。彼は次のように述べています。
「リン酸塩や上皮細胞が混ざり合った濁った比重の高い尿は、しばしばビタミンCの欠乏状態と関係していることをわたしは観察してきた。血中アスコルビン酸濃度を高める目的でビタミンCを投与すると、体内から排出された結晶性の沈殿物は魔法のように尿中から消えていく。この変化は通常、500〜2000mgのビタミンCを摂取してから数時間以内に起こることが多い」(9)
こうした効果は腎臓だけにとどまりません。マコーミック医師は、胆道、膵臓、扁桃、虫垂(盲腸に付属するリンパ組織)、乳腺、子宮、卵巣、前立腺などにできる結石にも、ビタミンCの摂取が有効であることを確認しています。さらに彼は「動脈硬化にともなうカルシウム性沈着物でさえも、ビタミンCの補給により改善の可能性がある」と述べています。
加えて、眼球内に生じたカルシウム沈着物も、数日以内にビタミンCを補給することで除去できる可能性があるとし、歯の根本的な問題である歯石についても、十分な量のビタミンCを摂取することで明らかに抑制できると述べています。
腎結石にまつわる誤解は、今も根強く残っていますが、ビタミンCの代謝と排泄のメカニズムを踏まえると、正しく摂取すればむしろ利点が多いといえるでしょう。
今からおよそ50年前、ウィリアム・マコーミック医師は次のように述べました。

「著者は、臨床および研究室での調査の結果、タバコ1本の喫煙によって体内の約25mgのアスコルビン酸(ビタミンC)が消費されることを発見した。この量は、ちょうど平均的な大きさのオレンジ1個に含まれるビタミンCに相当する。こうした知見に基づけば、ヘビースモーカーが食事だけで体内のビタミンC濃度を正常に保つのは極めて困難であると言わざるを得ず、この点からも、現代においてビタミンC欠乏が蔓延している理由が理解できるだろう」(10)
この発言がなされたのは1954年のことで、当時は医師自身が雑誌広告やテレビコマーシャルで「お気に入りの銘柄のタバコ」を宣伝していたような時代でした。そうした時代背景を考えると、この見解は極めて先見的かつ勇気ある意見だったといえるでしょう。
興味深いことに、「結石(calculi)」「タバコ(cigarettes)」「ガン(cancer)」「心血管疾患(cardiovascular disease)」「結合組織(connective tissue)」「コラーゲン(collagen)」といった、健康に深く関わるキーワードの多くが、いずれも頭文字に「C」を持っています。これは偶然の一致にすぎませんが、マコーミック医師はそれらの語をつなぐ共通因子として、実際の医療現場において「ビタミンC」という実体を導き出しました。
マコーミック医師は、目の前の患者と真摯に向き合う実地医療の中で、ビタミンC欠乏が関与している多くの病態を発見し、そのたびに、それを正しく補うことで治療効果をあげることに全力を尽くしてきたのです。
研究者たちは、大量のアスコルビン酸に加え、タンパク質とビタミンB群のサプリメントを併用することで、ヘロイン依存者が離脱症状を伴わずに使用を中止できたという報告を行っています。いわゆるメガビタミン療法としては比較的控えめな量である、1日10g程度のアスコルビン酸の摂取によって、ヘロインへの欲求が抑えられ、その後も薬物を使用しない状態を維持することができたとされています。(11)

こうした成果を踏まえると、ヘロイン中毒の治療において、メタドンのような別の依存性薬物を継続的に与え続けるよりも、栄養的なアプローチを通じて身体の恒常性を回復させる方が、はるかに健康的で持続的な解決策であると考えられます。
オーストラリアの先住民アボリジニの集団において、かつて極めて高かった乳幼児死亡率が、アスコルビン酸を乳児に十分量与えるようになってから劇的に低下したという報告があります。具体的には、死亡率が50%から2%以下にまで減少したとされています。この報告は約25年前に発表されたもので、研究者たちは「SIDS(乳幼児突然死症候群)」の主たる原因は、おそらく乳児における壊血病である可能性が高いと結論づけています。(12)
壊血病は過去の病気と見なされがちですが、実際には今もなお、特定の集団や状況下では深刻な生命リスクであり続けている可能性があります。ただし「壊血病はすでに根絶された」とする社会的な先入観が広く存在しているため、臨床の場において適切に診断されることはほとんどありません。

1948年、マコーミック医師は次のように記しました。
「外見を損なう皮膚下の線状の傷(皮膚線条)は、長年にわたって妊娠に伴う自然な結果だと考えられてきたが、実際にはビタミンCの欠乏により腹部の結合組織が脆くなった結果である」(13)
レンガ壁の強度は、実はレンガ自体ではなく、それらをつなぎとめるモルタルにあります。同様に、わたしたちの体の細胞を結び付けているのがコラーゲンであり、ビタミンCはそのコラーゲンの合成と強化に不可欠な栄養素です。
コラーゲンが豊富で、かつ強固であれば、細胞間の結合がしっかりと保たれ、皮膚の弾力や強度も維持されます。そのため、ビタミンCの十分な摂取によって皮膚線条――いわゆる妊娠線や肥満線のような皮膚の断裂痕――を予防できる可能性があることは、実際の観察からも確認されています。
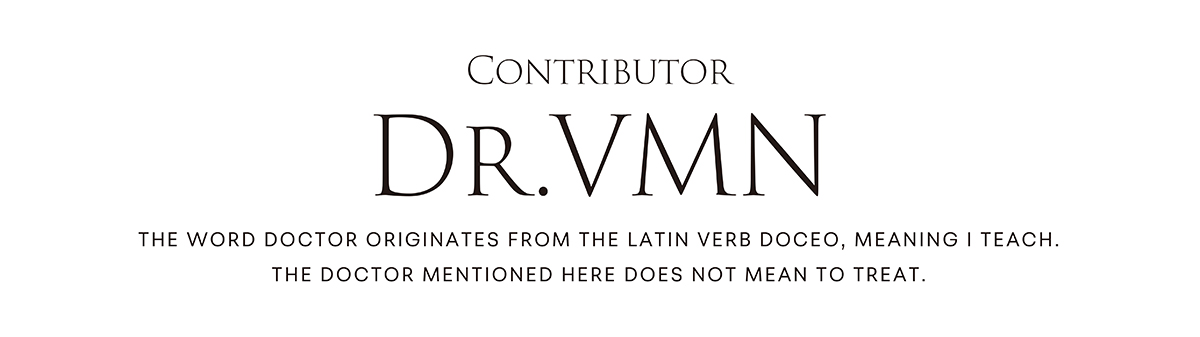
References
(1) Stone. “The Natural History of Ascorbic Acid in the Evolution of the Mammals and Primates and Its Significance for Present-day Man.” Stone. I. The Healing Factort Vitamin C Against Disease.
(2) Holmes. H.N.. K. Campbell, and E.J. Amberg. “The Effect of Vitamin C on Lead Poisoning.” / Lab Clin Med 24:11 (August 1939): 1119-1127.
(3) Klenner. “Observations on the Dose and Administration of Ascorbic Acid When Employed Beyond the Range of a Vitamin in Human Pathology.” Klenner. “Response of Peripheral and Central Nerve Pathology to Mega Doses of the Vitamin B Complex and Other Metabolites.
(4) Ibid.
(5) Stone. ‘The Natural History of Ascorbic Acid in the Evolution of the Mammals and Primates and Its Significance for Present-day Man.” Stone. The Healing Factort Vitamin C Against Disease.
(6) Cathcart, R. Vitamin C: The Non-toxic, Non-rate-limited, Antioxidant Free Radical Scavenger.’
Med Hypotheses 18 (1985): 61-77
(7) Curhan, G.C., W.C. Willett, F.E. Speizer, et al. “Intake of Vitamins Bo and C and the Risk of Kidney Stones in Women.” J Am Soc Nephrol 10:4 (April 1999): 840-845.
(8) Gerster. H “No Contribution of Ascorbic Acid to Renal Calcium Oxalate Stones.” Ann Nutr Metab 41:5 (1997)- 269-282.
(9) Mc Cormick, W.J. “Lithogenesis and Hypovitaminosis.” Med Record 159:7 July 1946): 410-413.
(10) Mc Cormick, W. J. “Intervertebral Disc Lesions: A New Etiological Concept.” Arch Pediatr NY 71 (January 1954): 29-33.
(11) Libby. A F„ and I. Stone. “The Hypoascorbemia-Kwashiorkor Approach to Drug Addiction Therapy: A Pilot Study.” / Ortho Molecular Psych 6 (1977): 300-308. Libby, A. F., J Day. C. R. Starling, et al. “A Study Indicating a Connection between Paranoia. Schizophrenia. Perceptual Disorders and I.Q in Alcohol and Drug Abusers.” J Ortho Molecular Psych 11 (1982): 50-66. Libby. A. F., C.R. Starling, F.H. Josefson, et al. “The ’Junk Food Connection’: A Study Reveals Alcohol and Drug Lifestyles Adversely Affect Metabolism and Behavior.” J Ortho Molecular Psych 11 (1982): 116— 127. Libby, A. F., C.R. Starling, D.K. MacMurray, et al. “Abnormal Blood and Urine Chemistries in an Alcohol and Drug Population: Dramatic Reversals Obtained From Potentially Serious Diseases.” J
Ortho Molecular Psych 11 (1982): 156-181.
(12) Kalokerinos. A. Every Second Child. New Canaan. CT: Keats. 1981.
(13) McCormick, W. J. “The Striae of Pregnancy: A New Etiological Concept.’ Med Record ‘August 1948).
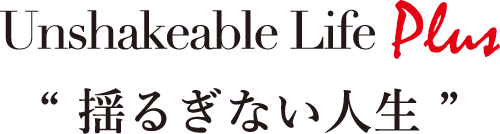 トップへ戻る
トップへ戻る