栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.06.27
ウィリアム・J・マコーミック医学博士は、多くの感染性疾患の根本的な原因はビタミンCの欠乏にあると考え、ビタミンCこそが効果的な治療法だと主張しました。1947年には、1840年以降の死亡統計を引用し、「結核、ジフテリア、猩紅熱、百日咳、リウマチ熱、腸チフスなどは、主としてビタミンCの不足に起因する」と述べています。(1)

感染症の歴史を、ビタミンCの摂取不足とその変動の歴史として読み解く視点は、今から見ても斬新で示唆に富んでいます。
マコーミック医師は、ビタミンCが治療の中心となる栄養素だと考え、「ビタミンCは還元剤として、時に酸化剤として働き、化学毒や細菌毒に対する特異的な拮抗作用を示す」と述べました。また、「組織内呼吸に関わる酸化還元反応において重要な役割を担い、抗体の産生や毒素の中和といった自然免疫形成にも関与している」とも述べています。
そのうえで、ビタミンCを1時間ごとに500〜1000mg、可能であれば静脈注射や筋肉注射で大量かつ繰り返し投与することで、アスコルビン酸の治療効果は極めて強力になるだろうと提言しています。(2)
ビタミンCを高頻度・高用量で投与することで感染症が治癒するという報告は数多くあり、こうした疾患が実は「ビタミン欠乏症」として再定義されるならば、ビタミンCを日常的にかつ大量に摂取することで予防が可能になると考えられます。マコーミック医師は次のように述べています。
「アスコルビン酸の大量投与によって、感染症の急性の発熱や毒性の段階をいったん抑えられれば、再発予防には比較的少量の維持投与で十分になることが多い。それはまるで、初期の火災には小さな消火器で足りるが、いったん大火になってしまえば消防車の高圧ホースが必要になるのと同じだ」(3)

1950年代当時、マコーミック医師が提案した「1回あたり1000mgを繰り返し投与する」という治療法は、当時としては信じられないほどの大量投与と見なされました。今日でも「ビタミンでそんな量を摂るのは危険だ」と思う人がいますが、実際には高用量のビタミンC投与は非常に安全で、ウイルス感染症に対して効果的であることが多くの研究で示されています。(4)
ビタミンCには、フリーラジカルを中和する抗酸化作用、ウイルスの殺傷活性の強化、そして免疫機能の強化といった多面的な働きがあります。定期的なサプリメント摂取は、ウイルス感染症の予防にも役立ちます。
クレンナー医師は、マコーミックよりもさらに大量のアスコルビン酸を用いることで、ウイルス感染症の治療に成功しました。彼はポリオに対して、ワクチン開発前から劇的な効果を報告しており、アスコルビン酸の結晶製剤が使用可能になって間もない時期には、感染させた猿を用いた研究で、ポリオの重症度を軽減し、免疫力を高めることが確認されました。(5)
ただし、ウイルスの感染量が多すぎたり、アスコルビン酸の投与量が少なかったりした研究では、明確な予防効果が観察されませんでした。(6) クレンナー医師や他の研究者たちが治療効果を得たのは、ビタミンCを非常に大量に用いたからだと考えられます。(7) 現在ではポリオの発症はほぼ抑制されていますが、これらの初期研究はアスコルビン酸の高い有効性と安全性を証明するものでした。
ワクチン接種の際には、副作用の可能性が少しでもある限り、ビタミンCをあらかじめ大量に摂取しておくべきだという意見もあります。

ウイルス性肝炎に対しても、ビタミンCの高用量投与は非常に効果的とされています。専門医ロバート・F・キャスカートは、「ウイルス性肝炎はビタミンCで最も簡単に治せる病気のひとつだ」と述べています。(8)
その投与量は経口で1日あたり40〜100g(4〜10万mg)に及ぶこともあり、腸が低用量で反応する場合には静脈注射での投与が推奨されます。急性肝炎では、通常3日以内に便や尿が正常化し、4日目には体調の回復を感じ、6日目には黄疸が消失することが多いとされます。慢性のケースでは、改善までにさらに時間がかかります。
ヘルペスにもアスコルビン酸は有効です。単純ヘルペス(口唇ヘルペス)、帯状疱疹、性器ヘルペスの3タイプがありますが、十分量のビタミンCでウイルスの再活性化を防ぐことができます。
ある研究では、1日1000〜2000mgのビタミンCを摂取した38人のヘルペス患者を追跡した結果、過去に3〜5回の発症を経験していた人のうち30人は、その後一度も再発しませんでした。他の患者も再発回数や重症度が減少し、8人中6人は1日3000〜4000mgに増量してから「非常に調子が良くなった」と報告しています。(9) なお、亜鉛との併用により、さらに相乗効果が得られます。
性器ヘルペスには、アスコルビン酸の局所外用が有効であるという報告もあります。アスコルビン酸自体は酸性のため、多少しみることがありますが、アスコルビン酸カルシウムを使えば無刺激で使用可能です。多くの人が、一晩で局所の痛みや腫れが著しく軽減したと報告しています。もし病変部に水疱があるならば、その液体にはウイルスが大量に含まれているため、周囲を含めて塗布するのがよいとされています。乾燥後はビタミンCの結晶が霜のように白く残ることがありますが、それを1日2回繰り返すことで、治癒が進むといわれています。
キャスカート医師は、「ビタミンCペーストの局所塗布は、単純ヘルペスに非常に効果的であり、やや効果は落ちるが、カポジ水痘様発疹症にも有効である」と述べています。(10) また、HPV(ヒトパピローマウイルス)にも同様の局所療法が有望とされています。
新聞や雑誌、さまざまなメディアでたびたび話題になる「鳥インフルエンザ」は、インフルエンザの中でも特に重症化しやすいタイプです。しかし、人への感染の大半は実際には家畜の豚由来であるため、「鳥インフルエンザ」よりもむしろ「豚インフルエンザ」と呼ぶべきかもしれません。

注目すべきなのは、鳥インフルエンザの症状の一部に皮下出血や鼻、歯ぐきからの出血が含まれるという点です。これらは臨床的には壊血病で見られる典型的な症状であり、深刻なビタミンC欠乏が存在していることを示しています。すなわち、ビタミンCがこの疾患に対して治療的に必要であることを意味しています。
重症例では1日あたり20万〜30万mg(200〜300g)あるいはそれ以上のビタミンCが必要となる場合があり、このレベルになると医師による静脈注射での投与が検討されます。これほどまでの高用量が必要になる理由は、鳥インフルエンザがエボラ出血熱のようなウイルス性出血熱に類似し、体内でビタミンCが急速に消耗されるためと考えられます。
ビタミンC療法に精通したキャスカート医師は、一般的なインフルエンザに対しては1日あたり10万〜15万mg(100〜150g)、鳥インフルエンザには1日15万〜30万mg(150〜300g)のアスコルビン酸が必要になる場合があると詳細に述べています。(11)
ビタミンC療法を成功させるためには、「適切な量を、適切な頻度で投与する」ことが絶対に必要です。基本的なルールはこうです。
「最良の結果を得るには、起きている時間帯にビタミンCを複数回に分けて摂取し、便がゆるくならない最大量まで増やすこと。便がゆるくなったら、用量を50%程度減らす。症状が再び現れたら、それは用量を増やす合図である。」
このようにして、十分な期間継続することで、ビタミンCがウイルス性疾患の重症度や持続期間をどれほど軽減できるか、自身で体験することができるはずです。
アスコルビン酸は、ウイルスだけでなく細菌感染症に対しても有効であるとされています。その理由として、以下の4点が挙げられます。
・細菌の増殖を抑える「制菌作用」があること
・細菌が産生する毒素を解毒する能力があること
・マクロファージなどの貪食作用(体内の異物を取り込んで分解する免疫反応)を維持・調整すること
・非毒性であるため、高用量の投与が安全に可能であること
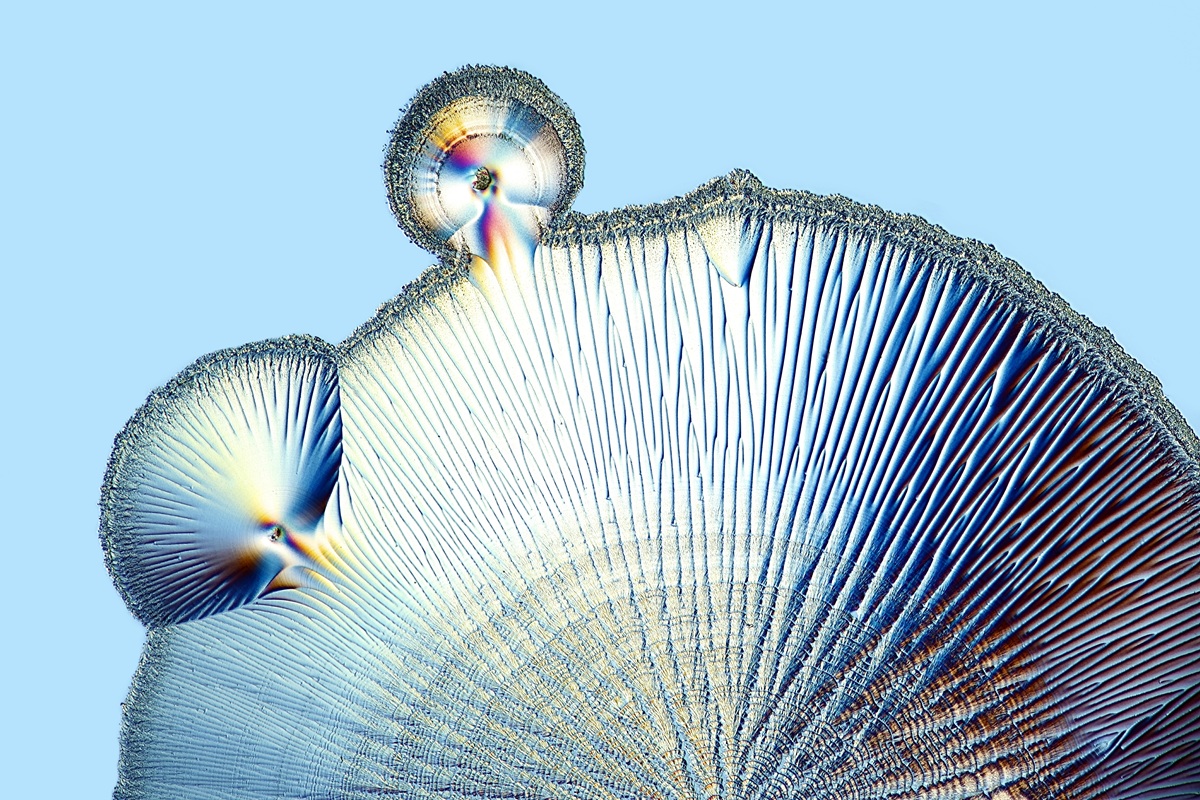
アスコルビン酸は、これまでも結核、肺炎、百日咳、腸チフス、赤痢、その他の感染症の治療に使われてきました。初期の研究では、現在の基準から見れば低用量でしたが、それでも一定の効果が確認されていました。
たとえば、マコーミック医師は50年前に、1日2〜4gのビタミンCで患者の症状が明確に改善したと報告しています。一方、クレンナー医師はその10〜20倍、すなわち20〜80gといったさらに高用量を推奨していました。
ビタミンC(アスコルビン酸)は、細胞と細胞を結びつける「生体のセメント」ともいえるコラーゲンの合成と強度維持に関与しています。細胞どうしが密に並び、結合組織が強固であれば、腫瘍細胞がその隙間を縫って浸潤・増殖することは難しくなるのではないか――この考え方は一見単純に見えるかもしれませんが、ガンの進展メカニズムに対する重要な一歩を示すものです。そして、このアイデアを最初に提唱したのがウィリアム・マコーミック医師でした。
彼は次のように述べています。
「ガンにおいては、コラーゲン合成を最適レベルに保つことで、ガン細胞の周囲の組織基質が強化される。すると、ガン細胞はその場から拡がることが難しくなり、周囲の組織を破壊して転移することができなくなる」(12)
この簡潔ながら力強い仮説こそが、ライナス・ポーリング博士とユーアン・キャメロン医師が、ガンに対して高用量のビタミンCを使うという決断を後押しした理論的背景でした。結局のところ、ガン細胞の転移を抑えるために、ビタミンCでコラーゲンの強度を高めるという発想は、極めて理にかなったアプローチだといえます。
マコーミック医師はまた、ガン患者の組織に含まれるビタミンC濃度が著しく低いことを早くから指摘した一人でもあります。彼によれば、ガン患者の体内では約4500mgものビタミンCが不足しているとされており、これはガンの進行を防ぐには不十分なコラーゲンの脆弱さを説明する要因の一つと考えられます。

さらに彼は、壊血病(古典的なビタミンC欠乏症)で現れる症状が、特定の白血病や他のタイプのガンで見られる症状と非常によく似ていることにも注目しました。現代では壊血病はまれな病気とされていますが、一方でガンは蔓延しています。このことからマコーミック医師は、「ガンと壊血病は、症状や進行、組織への影響が類似しており、実は根本的に同じ病態なのに、別の名前で呼ばれているだけかもしれない」という仮説を提唱しました。
ビタミンCの欠乏がコラーゲン合成を阻害し、それが結果として上皮組織や結合組織を脆弱化させ、細胞の秩序ある配列を破壊し、ガンの土壌を準備してしまうという考え方を、マコーミック医師は一貫して主張しました。(13)
彼の結論は次のようにまとめられます。
「わたしたちがガンに対してなすべきもっとも重要な取り組みは、細胞配列の乱れ――すなわち、上皮細胞層およびその下層にある結合組織(コラーゲン)の破壊――の予防に向けられるべきである。これらの細胞配列の乱れは、なかなか治らない傷や出血しやすさといった形で現れ、それらは将来ガンになる可能性を示す警告症状であるかもしれない。また、それは壊血病の初期症状でもある」(14)
もし、わたしたちの文明社会が「ガン」と呼んでいる多くの疾患の実態が、実は「慢性的な壊血病」だとするならば、それらの病気の症状や進行、そして予後には、ビタミンC欠乏という共通の原因が存在し、そして共通の治療法 ― つまりビタミンCの大量投与 ― があるということになります。
この仮説がたとえ部分的にでも正しいのであれば、すべてのガン患者は標準治療の一環として、大量のアスコルビン酸を投与されるべきだという主張は、決して突飛なものではなく、むしろ見過ごすべきでない重要な可能性と言えるでしょう。
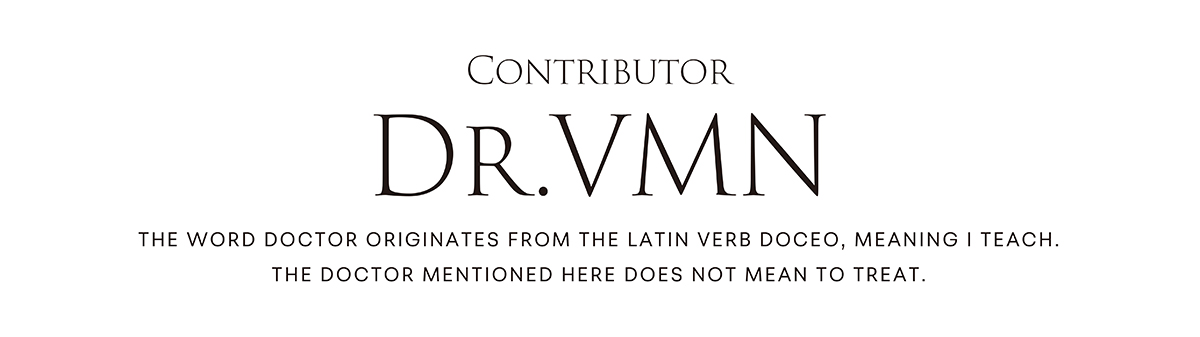
References
(1) McCormick, W. J. “The Changing Incidence and Mortality of Infectious Disease in Relation to Changed Trends in Nutrition.” Med Record (September 1947).
(2) McCormick, W. J. “Ascorbic Acid as a Chemotherapeutic Agent ” Arch Pediatr AT 69 (April 1952): 151-155.
(3) Ibid.
(4) Gorton. H.C., and K. Jarvis. “The Effectiveness of Vitamin C in Preventing and Relieving the Symptoms of Virus-induced Respiratory Infections.” J Manipul Physiol Ther 22:8 (1999): 530-533 See also: Smith, Lendon H. (ed). Clinical Guide to the Use of Vitamin CtThe Clinical Experiences of Frederick R. Klenner, M.D. Available online at: www.seanet.com/~alexs/.
(5) Jungeblut, C. W. “Inactivation of Poliomyelitis Virus in vitro by Crystalline Vitamin C (Ascorbic Acid)” J Exp Med 62 (1935): 517-521. Jungeblut, C.W. “Further Observations on Vitamin C Therapy in Experimental Poliomyelitis.” J Exp Med 66 (1937): 459-477. Jungeblut. C.W.”A Further Contribution to Vitamin C Therapy in Experimental Poliomyelitis.”/Exp Med 70 (1939): 315-332.
(6) Sabine, A. B. “Vitamin C in Relation to Experimental Poliomyelitis.” J Exp Med 69 (1939): 507-515.
(7) Klenner. F.R. “Recent Discoveries in the Treatment of Lockjaw with Vitamin C and Toluenol.” Tn-State Medical Journal (July 1954). Klenner. F.R. “Observations on the Dose and Administration of Ascorbic Acid When Employed Beyond the Range of a Vitamin in Human Pathology.” J Appl Nutr 23 (1971): 61-88. Klenner. F.R. “Response of Peripheral and Central Nerve Pathology to Mega-Doses of the Vitamin B-Complex and Other Metabolites.” J Appl Nutr 25 (1973): 16-40. Available online at www.tldp.com/issue/ll_00/klenner.htm. Stone. I “The Natural History of Ascorbic Acid in the. Evolution of the Mammals and Primates and Its Significance for Present-day Man.” J Ortho Molecular Psych 1 (1972): 82-89. Stone. I. The Healing Factort Vitamin C Against Disease. New York: Grosset and Dunlap. 1972.
(8) Cathcart, R.F. “Clinical Trial of Vitamin C.” (Letter to the Editor.) Medical Tribune (June 25, 1975).
(9) Lewin. S. Vitamin Ct Its Molecular Biology and Medical Potential. New York: Academic Press. 1976.
(10) Cathcart R.F. “Vitamin C in the Treatment of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).” Mtd Hypo theses 14:4 (August 19S4): 423-433. Available online at: www.doctoryourself.com/aids_
(11) Cathcart R_F. “Treatment of the Flu with Massive Doses of Vitamin C.” Available online at: cricmeiccm mystery.htrn=treaunent Cathcart R.F. “Avian (Bird) Flu.” Available online
(12) Stttte. I “The Genette Disease. Hypcascorbemia: A Fresh Approach to an Ancient Disease and
si Its Medical Implications.’ Acta Genet Med Gcmellolog 16:1 (1967): 52-60.
(13) McCormick. W. J. “Have We Forgotten the Lesson of Scurvy””” J Appl Nutr 15:1-2 (1962): 4-12. McCormick, W.J . “Cancer The Preconditioning Factor in Pathogenesis.” Arch Pediatr NY1\ (1954): 313 McCormick. W. J. “Cancer A Collagen Disease. Secondary to a Nutritional Deficiency?” Arch Pediatr 76 (1959): 166.
(14) McCormick. “Have We Forgotten the Lesson of Scurvy?”
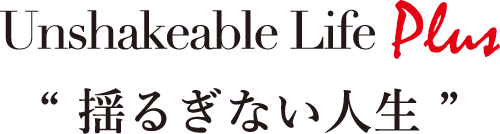 トップへ戻る
トップへ戻る