栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.06.20
アメリカでは毎年、心臓病や心臓発作によって数百万人が命を落としていますが、ビタミンCのサプリメントによって多くの命が救えるという明確な証拠が存在します。
ノーベル賞を2度受賞した科学者ライナス・ポーリング博士は、アメリカの成人が毎日2000〜3000mgのビタミンCを摂取すれば、心臓病の発症率を80%も減少させられると予測しました。
彼は「ビタミン欠乏こそが心臓病の最も一般的な原因であり、ゆえにビタミンCの補給は心臓病に対する普遍的な治療法である」と述べています。(1)

心臓病はアメリカにおいて死因の第一位です。すでに心臓病を患っている人に対して、ポーリング博士は、ビタミンCを1日6000mg、アミノ酸の一種であるリシンを同じく6000mg摂取することで、心臓の動脈閉塞を元の状態に改善できる可能性があると提唱しました。
ビタミンCの補給により、血中コレステロールを下げ、損傷した動脈壁の修復が可能になるとしています。
さらに、ビタミンCとビタミンEの併用は、動脈硬化の進行リスクを有意に減少させることが示されています。(2)
高齢者1万1178人(67〜105歳)を対象とした9年間にわたる疫学研究「EPESES(高齢者の疫学研究のための確立母集団)」では、ビタミンCとEを同時に摂取していたグループで、飲酒歴、喫煙歴、アスピリンの使用、病歴などの因子を調整した後でも、全死亡リスクおよび冠動脈疾患による死亡リスクが低下していました。(3)
さらに、8万5000人以上の女性看護師を16年間にわたって追跡調査した大規模な研究では、ビタミンサプリの摂取によって心臓病リスクが有意に低下したと報告されています。
この研究では、年齢や喫煙歴、その他の冠動脈疾患リスク因子を適切に調整したうえで、ビタミンCの高用量摂取が予防効果にとって重要であることが明らかになりました。(4)

また、国際研究チームが実施した解析では、ビタミンC、ビタミンE、そして数百種類のカロテノイド(自然界の色素群)の摂取と冠動脈疾患リスクの関連が評価されました。
これは健康な29万3000人を対象とした9つの前向き研究(プロスペクティブ・スタディー)のメタ解析であり、最大10年間の追跡調査も含まれています。
食事から摂取する抗酸化ビタミンにはわずかなリスク低減効果しか見られなかった一方で、1日700mgのビタミンCサプリメントを摂取していた人は、まったく摂っていなかった人と比べて、心疾患リスクが約25%減少していました。(5)
ビタミンCには、正常な血管壁の維持と血液循環の安定に関わる2つの重要な作用があります。
ひとつは、血管の強度と柔軟性を維持するために不可欠なコラーゲンの合成、もうひとつは、コレステロールを水に溶けやすい形に変える働きです。
もちろん、動脈硬化や冠動脈疾患、脳卒中の発症は食事全体の質や脂質、糖質、タンパク質の摂取バランスとも関連しており、非常に複雑な要因が関与しますが、アスコルビン酸が鍵を握る要素であることは確かです。
壊血病で見られるように、コラーゲン構造の脆弱性は、毛細血管の出血や歯のぐらつき、治ったはずの傷の再開などの症状に直結します。
ストレスによって体内のアスコルビン酸が枯渇しやすくなり、特に動脈の中でも機械的ストレスの強い部位では、その濃度が著しく低下する傾向があります。
初期の研究では、アスコルビン酸が欠乏すると、細胞間基質の構造が分解される「デポリメリゼーション(脱重合)」が起こることが明らかになっており、後の研究者は、そうした欠乏部位にアスコルビン酸を補うことで機能の回復が可能であると結論づけました。

コレステロールと動脈硬化の関係もよく知られています。
血中コレステロールが高い人は、動脈硬化や冠動脈疾患にかかりやすい傾向があります。
ビタミンCの欠乏は、体内でのコレステロール合成を活性化してしまいますが、アスコルビン酸を補給することで、ウサギやモルモット、ラット、さらにはヒトでもコレステロールの低下が観察されています。
特に、ビタミンB3(ナイアシン)と併用すると、より顕著な改善効果が得られます。
高コレステロールの人ほど、ビタミンCの用量を増やすことで、改善が目立つようです。
研究者たちは、血中コレステロール濃度はアスコルビン酸の摂取量によって大きく変動することを確認しています。(6)
動脈硬化は、実のところ長期的なビタミンC欠乏の結果と考えられるかもしれません。
アスコルビン酸には、血管内のプラーク(沈着物)に対して、2つの方法で作用することが知られています。
ひとつは表面張力を下げて沈着物を「洗い流す」ように働くこと、もうひとつは、プラーク中のカルシウムを除去する作用です。
アルビノラットに体重1kgあたり100〜200mgの高用量ビタミンCを投与した実験では、総コレステロール、LDL(悪玉コレステロール)、VLDL(超悪玉)すべてが低下しました。
この量は体重70kgの人間で換算すると、1日7000〜1万4000mg(7〜14g)に相当します。
研究者のM・U・エテングらは、中〜高用量のビタミンCが粥状動脈硬化の予防に有効である可能性があると述べています。(7)

フィンランドの「クオピオ虚血性心疾患リスク因子研究」では、2419人の中年男性を対象に、血中ビタミンC濃度と脳卒中リスクの関係が調査されました(すでに脳卒中の既往がある男性は除外)。
その結果、10年間の追跡調査中に脳卒中を発症したのは120人で、年齢、BMI、喫煙、血圧、血中コレステロールなどの要因を調整した後でも、ビタミンC濃度の低い人ほど発症リスクが2倍以上高いことが判明しました。(8)
脳卒中は、通常は血栓や塞栓によって脳への血流が遮断されて発症します。
動脈硬化が進んだ血管では、こうした血栓ができやすくなります。近年の研究では、特に高血圧と肥満を合併している男性で、血中ビタミンC濃度が低いことが、脳卒中の発症リスクと強く関連していると報告されています。(9)
さらに、ビタミンCには動脈壁の構造的な安定性を保ち、心血管組織全体の強化に関与する役割があります。
炎症マーカーであるCRP(C反応性タンパク)を減少させる効果も確認されており、慢性炎症が心疾患のリスク要因とされる今日、こうした作用は非常に重要です。(10)
わたしたちが日常的に「普通の風邪(common cold)」と呼んでいるものは、実際にはそれほど「共通している(common)」わけではなく、その多様性こそが風邪のやっかいな点です。
医学的に「風邪」とは、急性かつ短期間のウイルス性上気道感染症を指し、場合によっては細菌感染のあとに起こることもあります。
代表的な症状としては、全身のだるさ、腫れて湿った副鼻腔からの中程度〜重度の鼻水、そして軽い発熱などが挙げられます。一般的にはおよそ6日以内に自然に回復します。

しかし、ウイルス感染ではない鼻水の症状を抱えている人も多く、それはアレルギー性副鼻腔炎によるものです。
実際、大規模な集団を対象に「風邪薬」の効果を検証すると、ウイルス性の風邪とアレルギー性の風邪の両方が混在しており、両者は原因も異なれば治療法も異なります。
たとえば、抗ヒスタミン薬はアレルギー性の風邪に有効であり、抗菌薬は細菌性の感染に対して有効ですが、ウイルス性の風邪にはあまり効果がありません。
その一方で、アスコルビン酸(ビタミンC)は、これら三つのタイプすべてにある程度の効果を持ちますが、アレルギー性の風邪にはやや効果が劣るとされています。
なお、アレルギー性の風邪の背景には乳製品に対するアレルギーが関与していることもよくあります。
「風邪」という一括りの中に実はさまざまな病態が含まれていることを理解すれば、アスコルビン酸の治療・予防効果に関する議論も整理しやすくなります。
ホッファー博士の見解では、アスコルビン酸はウイルス性の風邪、つまり「本来の意味での風邪」に最もよく効くとされています。

ウイルス性の風邪には大きく2つのパターンがあります。
ひとつは寒さやストレスなどによって体内に潜んでいたウイルスが活性化し、血中のインターフェロンや抗体が低下することによって発症するタイプ。
もうひとつは、風邪をひいている人との接触や、くしゃみなどによる飛沫感染によって発症するタイプです。
アスコルビン酸は、体内のインターフェロンや抗体の濃度を高める働きがあり、この両方のタイプの風邪を予防する効果が期待できます。
ライナス・ポーリング博士は、複数の二重盲検試験において、1日わずか100mgのビタミンC摂取でも風邪の発生を45%、総死亡率を63%低下させたという報告が多数あることを明らかにしました。(11)
クレンナー医師は27年間にわたってウイルス性疾患の治療にアスコルビン酸を用い、「わたしの患者には、毎日10g(10000mg)以上を継続摂取している人が数百人いるが、その90%はまったく風邪をひかない。残りの10%も、さらに摂取量を増やせば風邪を予防できる」と述べています。(12)
1日1000mgの摂取で約45〜63%の効果、10000mgで90%の効果があるなら、サプリメントを摂っていない人が食事だけで摂っている100mg未満の量では、風邪予防は到底期待できないということです。
しかしながら、国の定めるRDA/DRIでは、妊婦を含む成人全般に対して「1日100mg以下で十分」とされているのが現状です。
研究によって、ビタミンCは風邪に対する最も安全で、最も安価で、そして最も効果的な予防および治療法であることが確認されています。(13)
ある研究では、715人を対象に、風邪やインフルエンザ症状が現れた被験者には最初の6時間に1時間ごとに1000mgを投与し、その後は1日3回の服用を続けました。
無症状の人にも予防として1日3回1000mgを投与したところ、実験群の症状は対照群と比べて85%改善しました。
「30年以上にわたり、ビタミンCの高用量投与は風邪やインフルエンザに有効であると考えられてきた」とH.C.ゴートンらは述べています。(14)

別の研究では、冬の60日間ビタミンCを摂取した群は、プラセボ群と比べて明らかに風邪の発症率が低く、仮に風邪をひいても、症状が軽く、回復も早かったことが報告されています。
バン・ストラテンらはこの研究結果から「ビタミンCは効果的である」と結論づけました。(15)
ビタミンCは、ウイルスの侵入を防ぐために結合組織を強化し、同時に免疫機能を高め、フリーラジカル(活性酸素)を中和し、非常に高用量では直接的な抗ウイルス作用もあるとされています。(16)
こうした複数の作用によって、風邪の発症頻度、重症度、そして持続期間を減少させる効果があると考えられています。
ある試験では、16人の男性に対して1日4回500mgのアスコルビン酸またはプラセボを投与する二重盲検試験が行われました。
全員が、風邪ウイルスに感染させられた他人8人と1週間生活を共にしました。
その後さらに2週間にわたって投与を継続した結果、プラセボ群の8人中7人が風邪を発症したのに対し、アスコルビン酸群では8人中4人の発症にとどまり、症状も軽度であったことが統計的に確認されました。(17)
ポーリング博士が主張していたとおり、風邪を予防するための最も有効な方法は、大量のビタミンCを摂ることです。
また、食事から精製糖を避けることも、予防効果を高める一助になります。具体的な方法としては、8時間おきに1000mgのビタミンCを摂取するのが一例です。
風邪の初期症状を感じたら、起きている時間帯に1時間おきに2000mgずつ摂取し、症状が消えるまでこの用量を継続するとよいとされています。(18)

それ以上の頻度で摂取している人もいます。もし腸がビタミンCに耐えられず下痢などの症状が出た場合は、用量を半分に減らすとよいでしょう。服用量が多いほど、風邪の回復は早く、効果も顕著になります。
最適な摂取量は「おならや下痢が出ないギリギリの量(緩下作用が出る直前の量)」とされており、個人によって必要量は異なります。
そのため、自分自身で試して最適量を見つけることが大切です。(19)
そうすることで、風邪にかからなくなり、医師にかかる必要もなくなる人が多くなるはずです。
一方で、必要な量が1日12g(12000mg)である人が、3gしか摂らなければ効果が出ない可能性があり、「ビタミンCは効かない」という誤解を生むことになります。
このような誤解によって、多くの医師がビタミンCに対して否定的な見解を持ってしまっているのが現実です。
十分な量のビタミンCを摂っている人は、実際には「医者いらず」なのです。
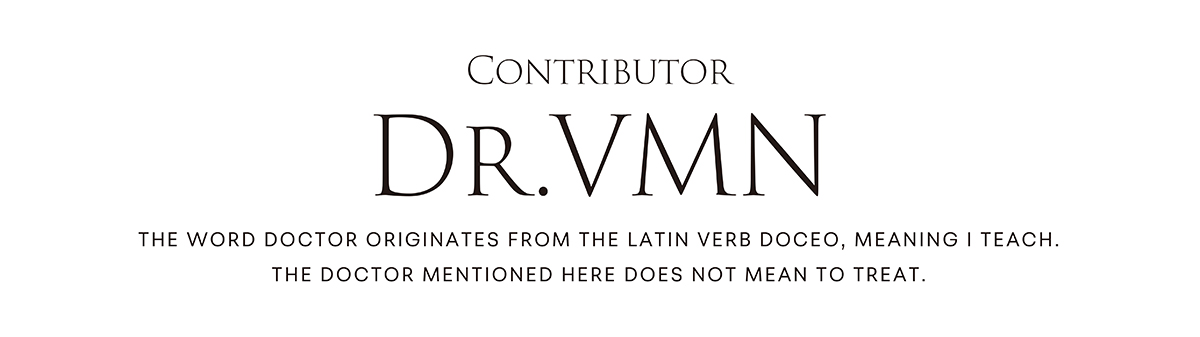
References
(1) Rath. M, and L. Pauling. “A Unified Theory of Human Cardiovascular Disease Leading the Way to the Abolition of This Disease as a Cause for Human Mortality.” J Ortho Molecular Med 7 (First Quarter 1992): 5.
(2) Ignore, L.J. “Long-term Combined Beneficial Effects of Physical Training and Metabolic Treatment on Arterioscleroses in Hypercholesterolemic Mice.” Proc Natl Acad Sci 101 (June 2004): 246-252.
(3) Losonczy, K.G., T.B. Harris, and R.J. Havlik. “Vitamin E and Vitamin C Supplement Use and Risk of All-cause and Coronary Heart Disease Mortality in Older Persons: The Established Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly.” Am J Clin Nutr 64:2 (August 1996): 190-196.
(4) Neale. R.J.. H. Lim, J. Turner, et al. “The Excretion of Large Vitamin C Loads in young an Elderly Subjects: An Ascorbic Acid Tolerance Test.” Age Ageing 17:1 (January 1988). 35-41.
(5) Knekt. P„ J. Ritz. M.A. Pereira, et al. “Antioxidant Vitamins and Coronary Heart Disease is A Pooled Analysis of 9 Cohorts.” Am J Clin Nutr 80:6 (December 2004): 1508-1520.
(6) Spittle, C. R. “Atherosclerosis and Vitamin C.” Lancet 2:7737 (December 1971): 1280-1281. Spittle.
C.R. “Atherosclerosis and Vitamin C.” Lancet 1:7754 (April 1972): 798.
(7) Eteng, M.U., H.A. Ibekwe. T. E. Amatey. et al. “Effect of Vitamin C on Serum Lipids and Electrolyte Profile of Albino Wistar Rats” Niger f Physiol Sci 21:1-2 (June-December 2006): 15-19.
(8) Kurl, S., T. P. Tuomaninen. J.A. Laukkenen. et al. “Plasma Vitamin C Modifies the Association between Hypertension and Risk of Stroke.’ Stroke 33 (2002): 1568-1573.
(9) Ibid.
(10) Block, G., C. Jensen, M. Dietrich, et al. “Plasma C-Reactive Protein Concentrations in Active and Passive Smokers: Influence of Antioxidant Supplementation.” f Am Coll Nutr 23:2 (2004): 141-147.
(11) Pauling, L. “The Significance of the Evidence about Ascorbic Acid and the Common Cold. Proc Natl Acad Sci USA 68:11 (November 1971): 2678-2681.
(12) Pauling, L. Vitamin C and the Common Cold. San Francisco: W. H. Freeman. 1970. See also: Pauling. L. “Ascorbic Acid and the Common Cold.’ Available online at: http://profiles.nlm.nih.gov/ MM/B/B/G/V/_/mmbbgv.pdf.
(13) Hemila, H. “Vitamin C and the Common Cold.” Br J Nutr 67:1 (January 1992): 3-16.
(14) Gorton, H.C., and K Jarvis. “The Effectiveness of Vitamin C in Preventing and Relieving the Symptoms of Virus-induced Respiratory Infections” J Manipul Physiol Ther 22:8 (1999): 530-533.
(15) Van Straten, M , and P. Josling. “Preventing the Common Cold with a Vitamin C Supplement A Double-blind, Placebo-controlled Survey.” Adv Ther 19:3 (May-June 2002): 151-159.
(16) Klenner, F.R. “Significance of High Daily Intake of Ascorbic Acid in Preventive Medicine. Megascorbate Ther 1:1 (1997). Available online at: www.vitamincfoundation.org/mega_l_l.html. Smith, Lendon H. (ed.). Clinical Guide to the Use of Vitamin C: The Clinical Experiences of Frederick R. Klenner, M. D. Available online at: www.seanet.com/-alexs/.
(17) Mink, K.A., EC. Dick, L.C. Jennings, et al. “Amelioration of Rhinovirus Colds by Vitamin C (Ascorbic Acid) Supplementation.” Paper presented at the 1987 International Symposium on Medical Virology, Los Angeles. California. November 12-14, 1987.
(18) Cathcart, R. F. “Vitamin C. Titrating to Bowel Tolerance. Anascorbemia, and Acute Induced Scurvy.” Med Hypotheses 7 (1981): 1359-1376.
(19) Cathcart, R.F. “Vitamin C in the Treatment of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).” Med Hypotheses 14:4 (August 1984): 423-433.Available online at: www.doctoryourself.com aids_ cathcart.html.
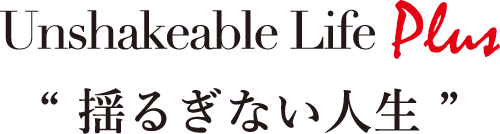 トップへ戻る
トップへ戻る