栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.04.11
先進国では、壊血病やペラグラといった古典的なビタミン欠乏症は稀ですが、これらの症状は外見的にも非常に顕著であり、しかも致命的です。

そのため、医学生に生化学を教える教授にとっては、いまだに主要なテーマとなっています。
しかし、先進国では実際にこれらの症状を目にする機会がほとんどないため、多くの医師は、こうした症状を見ても気付かない可能性があります。
このような古典的なビタミン欠乏状態は、例えばトウモロコシを灰汁煮沸処理せずに常食した結果ペラグラを発症するように、非常に単調な食事や飢餓が原因で起こります。
一種類の栄養素の欠乏が病気の発症に大きく関与しているかもしれませんが、実際には多くの栄養素が同時に不足していることがほとんどです。
人為的な生体実験によって、単一の栄養素が欠乏した状態を作り出すことは可能ですが、ビタミン「依存」状態に陥ることによっても、同様の状態が引き起こされる場合があります。
例えば、十分な栄養を摂取しているにもかかわらず、ビタミンB3「依存」になってしまう人がいます。
このような場合、ビタミンB3以外のすべての栄養素は十分に摂取されているものの、身体がビタミンB3を通常よりも多く必要としているため、供給が間に合っていない可能性があります。
統合失調症の急性期患者の中には、ビタミンB3の極端な不足によりペラグラの身体症状が出ているにもかかわらず、精神状態の異常が顕著なため、医師に見逃されているケースもあるかもしれません。

軽度のビタミン欠乏は、「健康」と「明らかな欠乏状態」の中間に位置する状態です。
特定の症状が明確に現れないため、外見からは判断が難しくなります。
ビタミン欠乏は徐々に進行し、最初に「先行段階」と呼ばれる状態が現れます。
この段階では、体内のビタミンやミネラルの貯蔵量がゆっくりと減少していきます。
次に訪れるのが「生化学的段階」です。
この段階では、体内の微量栄養素が枯渇し、それによって活性を発揮する酵素が十分に機能しなくなります。
しかし、外見上はまだ健康的に見えることが多いです。
その後、「生理学的段階」へと進行します。
この段階に至ると、酵素活性が著しく低下し、人格や行動の変化が見られるようになります。
具体的には、拒食症、うつ病、易怒性(ストレスによる過剰な怒りの爆発)、不安、不眠、眠気などの症状が現れることがあります。

最後の段階は「古典的欠乏」と呼ばれ、生命の危機に瀕する状態です。
この段階では、臨床的な変化や解剖学的な異常が明確に見られます。
最初の三つの段階は、「健康」と「古典的欠乏」の間に位置するため、「軽度の欠乏状態」または「無症候性欠乏」と呼ばれることがあります。
この概念は、約70年前に初めて提唱されました。
特定の栄養素が不足すると、複数の疾患が引き起こされることがあります。
例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、進行性筋萎縮症、進行性球麻痺(別名「舌口外口唇麻痺」)、原発性側索硬化症(別名「外側脊髄硬化症」)などは、それぞれ異なる疾患ではありますが、背景には長期間にわたるビタミン依存の問題が潜んでいる可能性があります。

フレデリック・R・クレンナー医師が、多発性硬化症や重症筋無力症の治療にオーソモレキュラー療法を用いて成功を収めたように、これらの疾患も栄養療法によって改善する可能性があるのです。[14]
無症候性ビタミン欠乏によって現れる症状や兆候は、驚くほど多様であり、さまざまな医学的・精神的症候群と類似しています。
医師は、これらの症状を特定の疾患の表れと考える傾向があります。
しかし、治療に反応しない場合、精神疾患と判断され、精神科へ紹介されることも少なくありません。
多くの医師は、患者の栄養状態を考慮することがほとんどなく、食事内容を詳しく調べることで診断の手がかりが得られる可能性があることを見逃しがちです。
もし患者が自ら選んだビタミンや他者に勧められたビタミンを摂取して回復した場合、医師はそれを「信念の力」や「プラセボ効果」、あるいは「自然寛解」として片付けてしまうことが多いです。
しかし、これは、栄養療法が「プラセボ効果」を劇的に向上させる可能性を示しているとも言えるでしょう。
栄養欠乏は、身体のすべての細胞や器官に影響を及ぼします。
細胞が正常に機能できない状態では、全身の健康が損なわれることになります。
全身的な症状としては、疲労感、倦怠感、緊張、全身痛、筋肉の過敏性亢進などが挙げられます。
また、特定の器官の機能が低下すると、その器官特有の症状が現れることもあります。

病気の原因を考える際に、甲状腺機能亢進症や感染症などの明確な疾患が見られず、疲労や不安、うつ症状がある場合には、栄養状態の問題がないか徹底的に調べるべきです。
特に、長期間のストレスを経験した後に症状が現れる場合、栄養欠乏が関与している可能性が高いです。
外科手術の前後や長期入院中の患者、胃腸の合併症や極端な体重減少、慢性感染症、がんやその他の病気による衰弱が見られる場合には、特に注意が必要です。
人によってビタミンの必要量には大きな個人差があり、同じ人でも時期によって変動します。
それでは、最適な摂取量をどのように決定すればよいのでしょうか?
最も効率的な方法は、試行錯誤を繰り返すことです。

現時点では、ビタミンの適切な摂取量を正確に判断できる臨床検査は存在しません。
体液中のビタミン濃度を測定することで、欠乏状態や欠乏の兆候を把握することは可能ですが、ビタミンB3、アスコルビン酸、チアミンが尿中に全く含まれていない場合、それらの体内濃度が著しく低下していることは明らかです。
しかし、医師はこのような深刻な欠乏状態に至る前に対処する必要があります。
なぜなら、ビタミン欠乏症が進行すると、死亡リスクが非常に高まるためです。
また、欠乏症がまだ明確に現れていない場合でも、無症候性の潜在的な欠乏が存在することがあります。
このようなケースでは、化学的な検査だけでは十分な判断ができません。
そのため、患者と主治医が協力して最適な摂取量を決定することが重要です。

「最適な服用量」とは、副作用がなく、健康を回復させるのに適した量のことを指します。
この定義に基づき、まず長年の臨床経験から症状に最も効果的とされる標準的な摂取量で治療を開始します。
その後、副作用がないことを確認しながら、効果が十分に現れるか観察を続けます。
患者と医師の双方が回復の進捗に満足している場合は、服用量を維持します。
一方で、回復が遅い場合は、より早い改善が見られるまで、あるいは副作用が出るまで、数週間から数か月ごとに少しずつ服用量を増やしていきます。
高用量のビタミンB3(ナイアシン)では、吐き気が副作用として現れることがあります。

ナイアシンの摂取量が多すぎると、吐き気や嘔吐が起こる可能性があり、さらに脱水や電解質異常を引き起こす危険性があります。
したがって、最適な摂取量は、吐き気を感じる量より1000〜2000mg少ない量とするのが適切です。
また、ビタミンCにはナイアシンとは異なる限界量があり、過剰摂取すると鼓腸(腸内ガスの増加)や下痢(Cフラッシュ)を引き起こすことがあります。
最適な摂取量は、これらの症状が現れない範囲内で、かつ治療効果が最も高い量となります。
一般的に、健康な人は多量のビタミンCを必要としませんが、ストレスが多い人や病気の人ではより高用量が必要になることがあります。
ビタミンCは緩下剤としても使用でき、一般的な市販の下剤よりもはるかに安全であると考えられていますが、現実的にはなかなかそうはならないようです。
例えば、エイブラム・ホッファー博士は、蚋(ぶよ)に刺された際に30gのビタミンCを摂取しましたが、下痢は起こらなかったと報告しています。
また、アンドリュー・W・ソウル博士は、ひどい風邪を治すために85gを摂取したこともあるといいます。

最適な摂取量で健康を回復した後、その量が多すぎる可能性があるため、維持量としてはやや少なめに設定するのがよいでしょう。
特に副作用がなくても、定期的に摂取量を見直すことが推奨されます。
健康維持に適した最適量(ヘルス・メインテナンス・オプティマム・ドウス)は、必要最低限の摂取量であるべきです。
減量は慎重に行い、減らした量で数か月様子を見てから、さらに次の減量を行うといった方法を取ります。
もし何らかの症状が再発すれば、すぐに用量を増やす必要があります。
また、特定のビタミンについては、維持量を一定以下にしない方が良いものもあります。
オーソモレキュラー診療医は、米国政府が推奨するRDA(推奨一日摂取量)が、治療指針としてほとんど役に立たないことを理解しています。
RDAやDRI(食事摂取基準)は、あくまでも「健康な人」を対象とした最低限の基準値であり、病気を抱えている人には適用できません。
アーサー・M・サックラー医師は、「ほとんどの人は何らかの健康上の問題を抱えている」と指摘しており、アルコール依存症、アレルギー、関節炎、糖尿病、高血圧の5つの症状だけを考えても、アメリカ国民の3分の1が該当すると述べています。
個々の患者に応じた適切な摂取量を決めるには、平均値を基準にするのではなく、個別の状況を考慮する必要があります。
サックラー医師は、「RDAがすべてのアメリカ人に当てはまるという考えは誤りであり、むしろ事実よりも誤情報が多い」と結論付けています。
さらに、DRIの改訂版も栄養摂取の基準としては不適切なものであると指摘されています。[15]
医師や学会、研究者で構成される委員会によると、RDA(推奨栄養所要量)およびDRI(食事摂取基準)の基準値は、速やかに引き上げるべきだとされています。

「ビタミンの安全性を再検討する独立委員会(IVSRP: インディペンデント・ビタミン・セーフティ・レビュー・パネル)」 は、この政府推奨の栄養基準について、「近年の栄養研究の進展に対応できていない」と批判しています。
その理由として、
現在の基準では摂取量が不十分であり、さらにその基準自体も適切ではないため、栄養欠乏や慢性疾患のリスクが高まるだけでなく、栄養不足にもかかわらず体重が過剰な人が増加する状況を招いている。
と指摘しました。
IVSRPは、多くの医師によるレポートや臨床研究を引用しながら、ビタミンB群(B1、B2、B3、B6、B12)、ビタミンC、D、E、およびミネラル(セレン、亜鉛、マグネシウム、クロム) の一日摂取量を大幅に引き上げるべきだと提言しています。
また、IVSRPは次のように述べています。
栄養欠乏は、症状として現れる場合はもちろん、無症候性の欠乏も含めて、現代社会が直面する最も深刻な健康問題の一因となっています。
がん、心血管疾患、精神疾患、その他の病気は、栄養摂取の不足によって発症や悪化のリスクが高まります。
しかし、科学的なエビデンスにより、適切な量の栄養素を摂取することで、これらの疾患を予防できることが証明されています。
新たな基準として、IVSRPは成人の最適な栄養摂取量を以下のように推奨しています。
IVSRPは最後に、次のように結論づけています。
一般的に、人々は加工食品を取り入れたバランスの良い食事をしていれば、必要な栄養素をすべて十分に摂取できると考えています。
しかし、これは誤った認識です。
十分なビタミンとミネラルを摂取するためには、未加工の多様な食品を日常の食事に取り入れ、さらにそれを補う形で適切な栄養サプリメントを活用することが重要です。
この考えを理想論で終わらせるべきではありません。
必ず実践すべきことなのです。 [16]
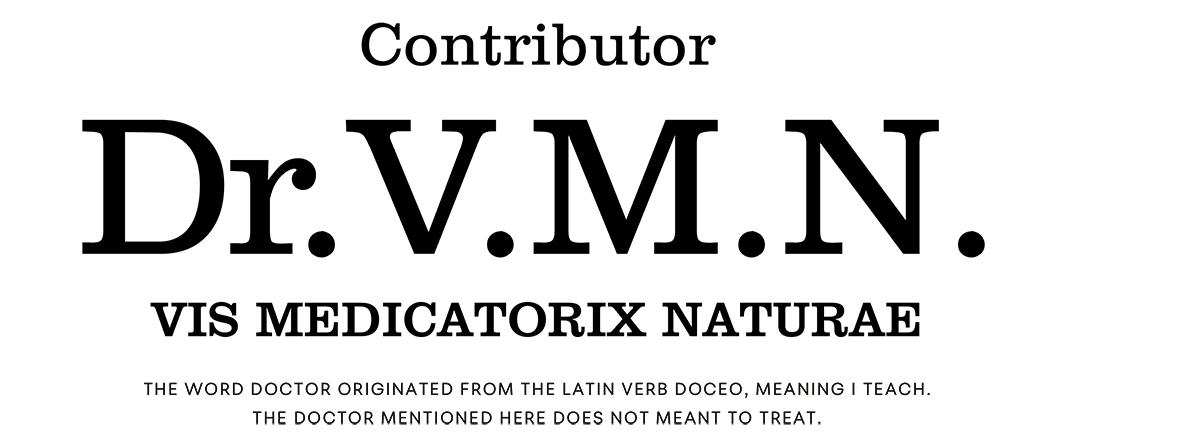
References
14. Smith. L. Clinical Guide to the Use of Vitamin C:The Clinical Experiences of Frederick R. Klenner, M.D. Tacoma,WA: Life Sciences Press. 1991.
15. Sackler,Arthur M. Nutr Rev (Fall 1985): 23.
16. “Report of the Independent Vitamin Safety Review Panel.” Orthomolecular Medicine News Service (May 23, 2006). Available online at: http://www.orthomolecular.org/resources/omns/ v02n05.shtml. “Vitamin Safety Review Panel Issues Follow-up Report” Orthomolecular Medicine News Service, (May 26, 2006). Available online at: http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v02n06.shtml.
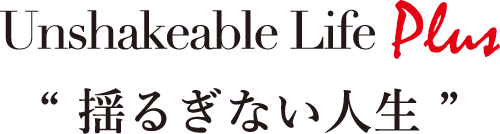 トップへ戻る
トップへ戻る