栄養
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
Nutrition
あなたは、あなたが食べてきたそのものです
2025.04.04
「依存(デペンデンス)」こそが、生命の本質であると言えます。

私たちの身体は、食物・水・睡眠・酸素に依存しており、さらには体内での化学反応もビタミンに絶対的に依存しています。
十分な量のビタミンを摂取できなければ、健康を損ない、病気になる可能性が高まります。
ビタミンが長期間欠乏すれば、最終的には命に関わることもあるのです。
このように、ビタミンへの依存は単なる概念ではなく、生存に不可欠なものなのです。
長期間にわたる栄養素の欠乏により、その栄養素の必要性が極端に高まることがあります。
その結果、通常の食事や低用量のサプリメントでは補えないほどの深刻な欠乏状態に陥ることがあります。
各種のビタミン欠乏症は、平均的なビタミン必要量の人がビタミンが不足した食事を続けることで発症します。
このような食事は、ビタミンだけでなくミネラルも不足していることが多いのです。

食事から必要な栄養素を十分に摂取できない場合、「相対的な欠乏」が生じます。
特に、必要量が非常に多く、理想的な食事をしても補えないほど深刻な場合には、栄養素の「相対的欠乏」状態が発生していると考えられます。
この場合、欠乏の原因は単なる栄養不足ではなく、特定の栄養素に対する体内の要求が異常に高まってしまっていることにあります。
このような状態を「依存」と呼びます。
したがって、栄養素に対する「依存」も、広義の「相対的欠乏」の一形態であると考えられます。
栄養「欠乏」も栄養「依存」も、病気として現れることに変わりはなく、その発症メカニズムが異なるだけで、結果は同じなのです。
栄養「依存」は、生まれつきの先天的なものと、後天的なものの両方が存在します。

遺伝的要因も関係しており、胎児期から発育の過程で染色体の正常な働きに必要な栄養素が不足していた場合、生まれながらにして栄養依存を抱えることがあります。
また、個々人にとっての最適なビタミン必要量も遺伝的要因によって大きく左右されます。
ビタミンは全身の細胞に行き渡らなければなりませんが、そのためには生体組織に浸透し、細胞膜を通過し、細胞内に届けられる必要があります。
このビタミン輸送の各機構は、ビタミンが存在することで正常に機能します。
効率的なビタミン輸送機構を持っている人は、そうでない人よりも必要なビタミン摂取量が少なくて済むでしょう。
例えば、悪性貧血はビタミンB12を効率的に吸収できないために発症します。
そのため、悪性貧血の患者には消化管を経由せず、注射によって直接ビタミンB12を補う必要があります。
後天的なビタミン依存もあります。
多くの場合、栄養不足に加え、ストレスが長期間続いた結果として生じます。
例えば、重度の栄養不足に加え、外科手術の前後に数週間続くストレスによってビタミン依存状態になることもあります。
現代の病院では、患者にとって適切な栄養補給の重要性が十分に認識されていません。
実際に、入院中に食事を与えられなかったことが原因で、疲労・緊張・鬱といった症状を発症する高齢者は少なくありません。

ある患者は2週間もの間、食事を与えられず、ようやく提供された食事は、ゼラチンとソフトドリンクという栄養価の低いものでした。
このような状況では、高用量のビタミン補給が回復のために不可欠だったのです。
後天的な栄養依存が最も顕著に示された例は、第二次世界大戦中の「実験」によるものです。
戦争中、連合国側の兵士の中には、日本の戦時捕虜として数年間過ごした者がいました。
カナダ人兵士は、タンパク質・脂質・カロリー・ビタミン・ミネラルの極度の不足に苦しみました。
栄養不足と精神的ストレスが相まって、急激な老化が進行するという臨床症状が観察されました。

これらの兵士たちは、ビタミンB3(ナイアシン)に対する依存状態にありました。
高用量のビタミンB3を摂取することで健康を取り戻し、その後もこの用量を維持することで初めて健康が保たれたのです。
彼らは複数の栄養素に対して依存状態にあった可能性がありますが、大半の退役軍人がナイアシンの補給によって著しく改善したことから、主にビタミンB3への依存が原因であったと考えられます。
彼らの老化は著しく、1年間捕虜生活を送ることで、通常の5年分に相当する老化を経験したとされています。
例えば、4年間捕虜として過ごした60歳の退役軍人は、収容所生活を経験していない80歳と同程度に老け込んでいたのです。
このような事例からも、栄養依存が健康と老化に及ぼす影響の大きさが理解できるでしょう。
65年前、栄養学者たちは、慢性的なペラグラ患者の中には、通常の少量のナイアシン治療では回復しない者がいることを観察しました。
彼らが驚いたのは、そうした患者たちが1日に1000mgものナイアシンを必要としていたことです。
つまり、少量のナイアシンではペラグラの症状が消失しなかったのです。
しかし、当時の彼らには、この理論と観察の間にある矛盾を説明することができませんでした。
しかし現在の視点から見ると、慢性的なペラグラがビタミンB3依存を引き起こしていたことは明らかです。
この結論は、犬を用いた実験によっても裏付けられています。

ナイアシン欠乏により舌が黒く変色する犬のペラグラ(黒舌病)に罹った犬は、発症直後にビタミンB3を少量投与されると回復しました。
しかし、黒舌病の状態のまま寿命の3分の1ほどの期間放置された犬は、回復するのにより多くのビタミンB3を必要としました。
このように、ビタミンB3の必要量については強固なエビデンスがありますが、その他のビタミンに関しても、慢性的な欠乏が依存を引き起こすと考えられています。
さらに、栄養依存に起因するさまざまな疾患を予防するのに必要な栄養素の摂取量は、「栄養欠乏指標疾患(index disease)」を防ぐのに必要な量よりも多いことが分かっています。
かつては、ビタミン依存性疾患の概念は食事の調整に重点を置いて考えられていましたが、現在では、体の組織が本当に必要としているものを考慮することが重要視されています。[13]
特定の栄養素(例えば特定のビタミン)における「欠乏」と「依存」の違いは、患者に投与すべき用量の違いにあります。
高用量の栄養療法によって救われた患者たちは、ビタミン依存の概念を支持しています。
また、高用量の栄養素を急に不適切な方法で中止した際に現れる症状も、ビタミン依存を理解するための分かりやすい例となります。
例えば、低用量のビタミンCを摂取していた人がそれをやめると壊血病になるのと同様に、高用量のビタミンCを摂取していた人が急にやめると、一連の症状が現れる可能性があります。
この現象は「反跳性(リバウンド)壊血病」と呼ばれ、高用量療法によって消失していた症状が再燃するだけでなく、壊血病の古典的な症状も含まれることが知られています。
要するに、体が必要としているものを求めるのは自然なことであり、これこそが「依存」の本質です。

アルコール依存症や薬物依存症による破壊的な影響については小学校で教えられていますが、一方で、好ましい栄養素への「依存」を無視した場合に生じる影響については、医学誌でさえほとんど議論されていません。
遺伝・食事・薬剤・疾患によって引き起こされるビタミン依存は、医学界では単なる医学的好奇心の対象と見なされています。
特に、統合失調症の患者が高用量のナイアシン(ビタミンB3)を必要とするという考え方は、精神医学の分野では異端とされています。
しかし、これは決して驚くべきことではありません。
ビオチン(ビタミンB群の一種で、かつては「ビタミンH」と呼ばれていました)やビタミンEが健康にとって必須であると医学界が認めるまでには、何十年もの時間がかかりました。
栄養学の分野では、特定の栄養素の欠乏が特定の疾患を引き起こすという考え方は、長らく確立された教義のように扱われてきました。
しかし、古典的に認められている少数の例外を除けば、多くの疾患に対してメガビタミン療法を行い、治療成功を報告してきた医師たちの膨大なデータを説明するには、この教義だけでは不十分です。
1つの栄養素が多くの異なる病気を治療できる理由は、1つの栄養素の欠乏が多くの異なる病気を引き起こしているからです。
これは、オーソモレキュラー療法の基本法則の1つと言えるでしょう。
「栄養欠乏」が「不十分な摂取量」に起因するものであるならば、「栄養依存」は「高まった必要量」に起因するものです。
乾燥したスポンジが牛乳を吸収するように、病弱な体は一般的に高用量のビタミンを必要とします。
そのため、ある疾患を治療するのに必要な栄養素の量は、患者の欠乏の度合いによって異なります。
したがって、私たちが扱っているのは「ビタミンの高用量(メガ・ドウス)」ではなく、「栄養素の高度欠乏(メガ・デフィシェンシー)」なのです。
オーソモレキュラー療法を実践する者は、治療において「これくらいなら効くだろう」と思う量を用いるのではなく、明確な結果を得られる量を用いるべきであることを知っています。

レンガの壁を作るための第一のルールは、まず十分なレンガを用意することです。
同様に、病んだ体は多くのビタミンを高用量で必要とするのです。
医師は、その必要性を満たすこともできますし、無視して患者を不必要に苦しませることもできます。
医学界全体がオーソモレキュラー療法を十分に受け入れるまでは、「医学とは、有毒な化学物質を栄養不良の人に投与し、その影響を観察する人体実験である」と言っても過言ではないでしょう。
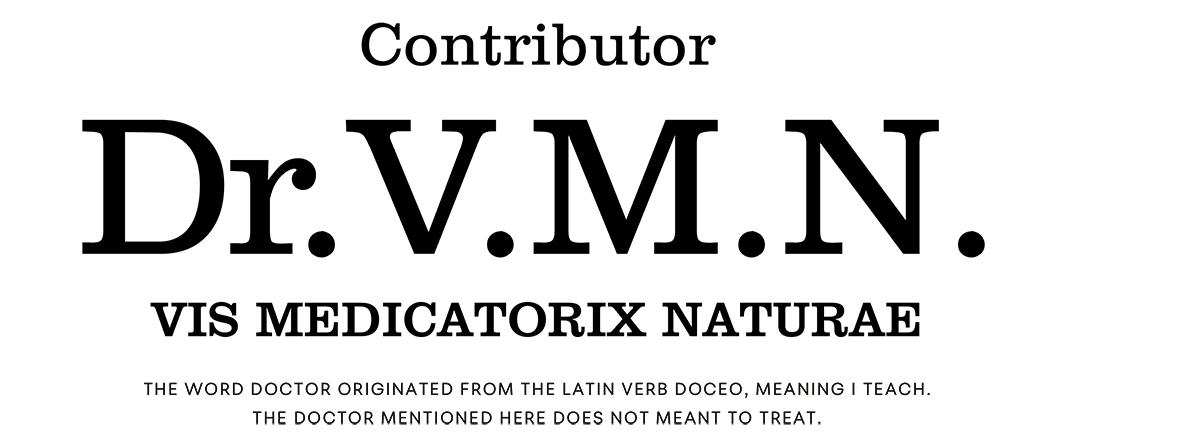
Reference
13. Hoffer.A.“Mechanism of Action of Nicotinic Acid and Nicotinamide in the Treatment of Schizophrenia.” In Hawkins. D.. and L. Pauling. Orthomolecular Psychiatry:Trcatmcnt of Schizophrenia. San Francisco:W.H. Freeman. 1973, pp. 202-262.
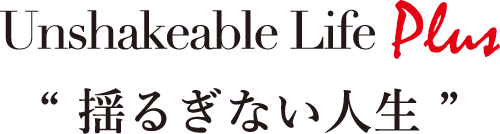 トップへ戻る
トップへ戻る