⒐ 健康に良い食物・悪い食物は科学的に明らかになっている
2025.05.23
目次
健康に良い vs. 悪い食べ物は、明らかになっている
―― 科学が証明した食品ランキング
経済最優先の社会環境においては、メディア、食品業界、ほとんどの有名シェフたち、料理本の著者たち、そしてわたしたちの政府はどれも、もっとも健康的な食べ方について正確なアドバイスを提供してくれていません。
ほとんどのキーワードは、ヘルシーではなくて、「美味しい」なのです。
つまり、ビジネスが優先ということです。
より正しい判断のためには、科学的根拠にもとづく知見が重要です。
『世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事』(二〇一八年東洋経済新報社)の著者で、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)内科学助教授・医学博士津川友介氏は、多くの最も信頼性が高い研究手法(メタアナリシス)によって「健康に良い食物・悪い食物」は科学的に明らかになっていると論じています。
健康に良い食物は、魚、野菜と果物、茶色い炭水化物、オリーブオイル、ナッツ類で、健康に悪い食物には、赤身肉や加工肉(ハムやソーセージ)、白い炭水化物(ジャガイモを含む)、バターなどの飽和脂肪酸が挙げられています。

Raw beef steak, chicken breast, and salmon
〝メインディッシュは肉と魚のどちらがいいのか?〞という問題がしばしば議論されますが、言うまでもなく「魚」に軍配が上がります。
まず魚に含まれるオメガ3脂肪酸は、心臓病予防などに効果が証明されており、人間の体に有益と言われています。
また魚そのものに関しては、67万人のデータを解析したメタアナリシス(メタ分析)で、魚の摂取量が1日60g増加すると死亡リスクが12%も低下したというデータがあります。[1]
さらに、週に1~2回、オメガ3脂肪酸であるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)を含んだ魚を摂取していた人は心臓病での死亡リスクは36%、トータルの死亡リスクは17%低下したという論文も存在します。[2]
では鶏肉はどうでしょうか?
〝肉か魚か〞といった二者択一ではなく、白身肉(鶏肉)への変更も有効です。
この白身肉に関しては、現在のところ人体への有害性は証明されていません。
167万人のデータを解析して赤身肉・加工肉と白身肉の人体への影響を調査した研究では〝赤身肉や加工肉をよく食べた人は心臓病や死亡リスクが上がったのに対して、白身肉を食べていた人は特に変わらなかった〞という結果も出ています。[3]
「地中海食」の神話とその限界
―― オリーブオイルは健康か、それとも控えるべきか?
一九九〇年代から健康に良いと言われてきた「オリーブオイル」は、フランスにあるジョセフ・フーリエ大学のミッシェル・デュロルジュリル博士らの研究グループによる「リヨンダイエット心臓研究」に基づいています。
そしてこの研究が提唱したのが、一九五九年にミネソタ大学の栄養学者アンセル・キーズが、著した『健康な食生活を送る方法(How to Eat Well and Stay Well)』という本の中で勧めている「地中海食」です。

地中海食は、果物や野菜、穀物、イモ類、ナッツ類、オリーブオイルを中心に動物性食品を少量摂るといったスタイルの食事です。
研究では「地中海スタイルの食事」をしたグループに心臓病が発生する可能性が、50〜70%低かったことから「心臓によい」オイルとして、メディアが広く報じたことがきっかけとなって社会に定着していきました。
しかし近年の研究では、オリーブオイルの14%〜17%は動脈を詰まらせるタイプの飽和脂肪で、冠動脈疾患の進行を遅らせるかもしれないが、この病気の進行を止め、症状を回復に向かわせることはできないと、いくつかの研究で報告されています。
ことに心臓病に関して、エセルスティン博士などは、声を大にして〝NO OIL!〞を強調しています。
コーヒーは脳と体を守る?
―― アルツハイマー予防に効果を示した研究
ひょっとしたら健康に良い食品に分類されている「コーヒー」ですが〝コーヒーが脳を守る〞という研究を、スェーデンのカロリンスカ研究所のミーア・キヴィペルト(Mia Kivipelt)教授らが報告しています。
これはフィンランドの65歳から79歳の1409人を平均21年間にわたって調査したもので、1日にコーヒーを全く飲まない人から2杯飲む人を「低レベル」、3から5杯までを「中レベル」、5杯以上飲む人を「高レベル」に分類して行ったものです。
その結果は、中レベルの人は、低レベルの人に比べて、アルツハイマー病発症率が65%も下回ったということです。

また研究者たちは、マイクロバイオームの働きによって、コーヒーが二型糖尿病や心臓発作、アルツハイマー病、さらには、ガンや新血管疾患のリスクを下げることがはっきりしていると結論しています。
コーヒーや赤ワインには、ポリフェノールが豊富に含まれています。
ポリフェノールとは、体内の活性酸素を抑制する「抗酸化物質」の総称で、さまざまな慢性病(生活習慣病)に効果があると言われています。
それが健康成分として表舞台に登場したのは、一九九二年に仏国ボルドー大学の研究グループが、赤ワインと動脈硬化の関係を発表したことがきっかけでした。
さて、食生活の中でもっとも豊富に摂れる解毒剤であるポリフェノールは、平均して毎日1gほど摂取されていると推計されています。
憶えておいていただきたいのは、体がポリフェノールを抽出して使う能力は、主としてマイクロバイオーム(腸内常在細菌)がコントロールしているということです。
つまり、ポリフェノールを最大限に活用するためには、善玉菌優勢の健康な腸内細菌叢を作ることが必要なのです。
内側からキレイが大切ですね。
Column「ブルーボトル」伝説とコーヒーの歴史
コーヒーが飲まれるようになったのは、西暦八五〇年ごろのアラブ人によってです。
それがヨーロッパに知られるには、七世紀もかかりました。
一五八〇年・トルコ産がイタリアに。一六四三年・パリで人気が高まる。
一六五〇年・オックスフォードに、初のコーヒーハウス開店。
一六八三年・ウィーンにも開店。ここのが最も有名です。
伝説上の最初のウィーンのカフェ:カフェ・アフメット(Café A.)
1683年の第二次ウィーン包囲の後、オスマン帝国軍が敗走する際にコーヒー豆の袋を置き去りにしたという話があります。
そのコーヒー豆を手に入れたゲオルク・フランツ・コルシツキー(Georg Franz Kolschitzky)が、ウィーンで最初のカフェを開いたというのが伝説です。
その店の名前は、記録に明確に残ってはいませんが、しばしば「ブルー ボトル(Blue Bottle)」という英語名で紹介されることがあります。
創業:1683年頃
創業者:ゲオルク・フランツ・コルシツキー
店名(伝説):ブルー・ボトル(Blue Bottle Café)
場所:ウィーン市内(現:ブルー・ボトル通り付近)
ちなみに、コーヒーを挽いた粉1ポンド(453g)には、コーヒーの木の1本になる豆を必要とします。
ココアやチョコレートは、悪魔の誘惑と信じられていた時代もありました。
原産地は南米で、十八世紀ごろの中米への移民は、村によっては60歳以下は口にしてはならず、教会から破門される場合もありました…参考までに。
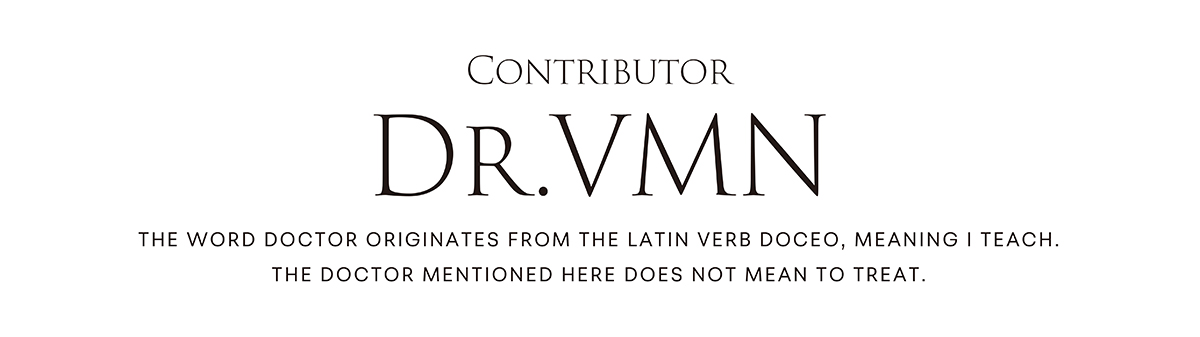
References
1. LG Zhao,et al. Fish consumption and all cause mortality: a metaanalysis of cohort studies. Eur J Clin Nutr. 2016 Feb;70(2):155 61.
2. Dariush Mozaffarian,et al. Fish Intake, Contaminants, and Human Health Evaluating the Risks and the Benefits. JAMA. 2006;296(15):1885 1899.
3. Itziar Abete,et al. Association between total, processed, red and white meat consumption and all cause, CVD and IHD mortality: a meta analysis of cohort studies. Br J Nutr. 2014 Sep 14;112(5): 762 75.
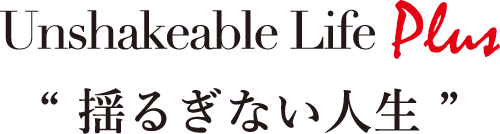 トップへ戻る
トップへ戻る
